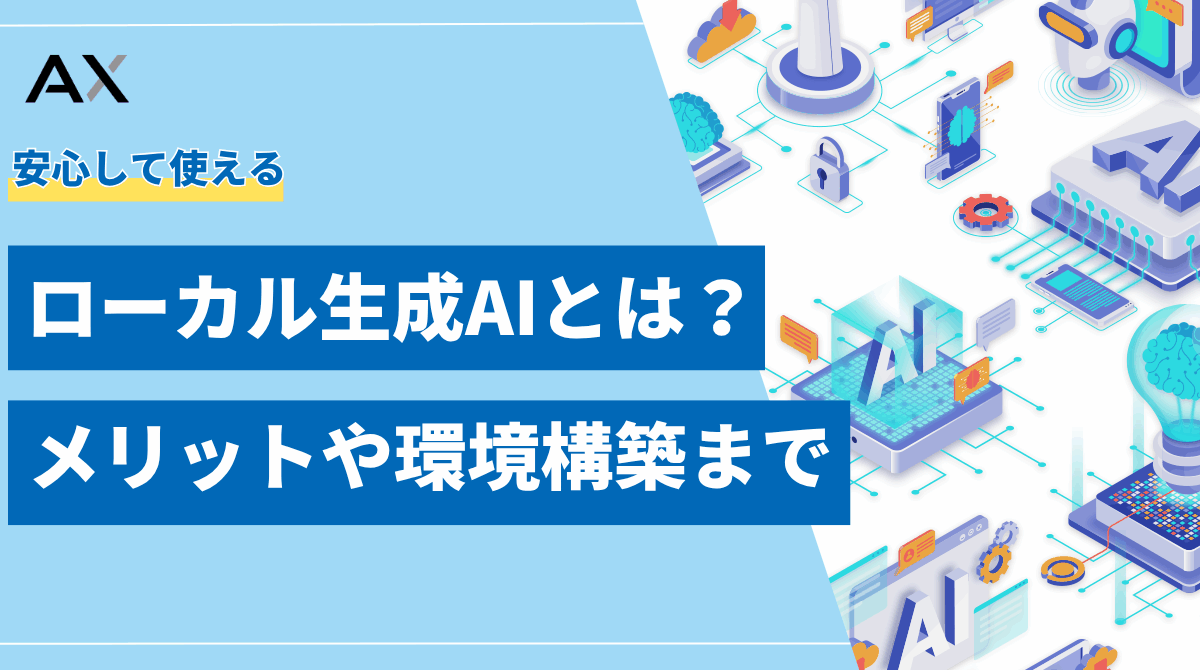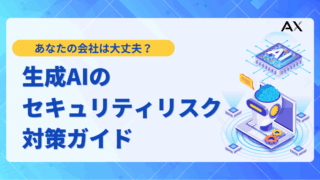生成AIを業務に活用したいものの、クラウドサービスは情報漏洩のリスクが懸念される、あるいは利用コストが予測しづらいといった課題を抱えていませんか。
機密情報を扱う性質上、AI導入に踏み切れない企業も少なくないでしょう。その解決策として今、注目を集めているのが「ローカル生成AI」です。手元のPCや自社サーバー上でAIを動作させることで、セキュリティを確保し、オフライン環境でも安定した利用が可能です
この記事では、ローカル生成AIの基本的な仕組みから、クラウド型との違い、具体的なメリット・デメリット、さらにはおすすめのモデルや環境構築のステップまで、導入を検討する上で必要な情報を網羅的に解説します。自社の状況に合わせて、安全かつ高効率なAI活用の第一歩を踏み出すためのヒントが満載です。AI導入の具体的な進め方や研修について知りたい方は、AX CAMPのサービス資料もぜひご覧ください。
ローカル生成AIとは?クラウド型との違いを解説

ローカル生成AIとは、インターネット上のクラウドサーバーを利用せず、手元にあるPCや自社内のサーバーに直接インストールして使用する生成AIを指します。ユーザー自身の管理下にある環境(ローカル環境)で全ての処理が完結するため、外部とのデータ通信が発生しにくい点が大きな特徴です。これにより、セキュリティやプライバシーの面でクラウド型にはない利点を提供します。
近年、AIモデルの軽量化やPCの性能向上は目覚ましく、これまで高性能なサーバーでしか動かせなかった大規模言語モデル(LLM)などが、個人や企業のPCレベルでも十分に扱えるようになってきました。この技術的進歩が、ローカル生成AIの普及を後押ししています。
手元のPCでAIを動かす仕組み
ローカル生成AIは、AIモデル本体と、それを動かすためのソフトウェアを手元のコンピュータにインストールして利用します。具体的には、「Llama 3」などオープンに利用可能なAIモデルをダウンロードし、「Ollama」や「LM Studio」といった実行環境ツールを使って動作させるのが一般的です。ただし、モデルのライセンスは個別に異なるため、商用利用等を検討する際は各モデルの利用規約を必ず確認する必要があります。
ユーザーが指示(プロンプト)を入力すると、PCに搭載されたGPU(Graphics Processing Unit)やCPUが計算処理を行い、結果を生成します。モデルのダウンロードやアップデートにはインターネット接続が必要ですが、一度セットアップすれば、基本的に外部サーバーにデータを送らずに処理できます。この点がセキュリティ上の大きな利点となります。
クラウド型生成AIとの決定的な違い
ローカル生成AIとクラウド型生成AI(例:ChatGPT, Geminiなど)の最も大きな違いは、AIが動作する「場所」にあります。クラウド型はサービス提供者のサーバー上でAIが動作し、ユーザーはインターネット経由でアクセスします。対照的に、ローカル生成AIはユーザー自身のPCやサーバー上で直接動作します。
この「場所」の違いが、セキュリティ、コスト、カスタマイズ性、応答速度といった実用上のあらゆる側面に影響を与えます。以下の表で、両者の主な違いを整理しました。
| 項目 | ローカル生成AI | クラウド型生成AI |
|---|---|---|
| 動作環境 | 自社のPCやサーバー(オフライン運用可) | サービス提供者のサーバー(オンライン必須) |
| セキュリティ | 適切に設定すれば外部送信を抑えられ、セキュリティ向上が期待できる | 外部サーバーに送信されるが、法人向けプランでは保護される |
| 応答速度 | ネットワーク遅延がなく高速(PCスペックに依存) | ネットワーク環境に依存し、遅延の可能性あり |
| カスタマイズ性 | 独自データで自由にチューニングでき、非常に高い | 提供される範囲内での限定的なカスタマイズ |
| 導入コスト | 高性能なハードウェアへの初期投資が必要 | 初期投資は不要な場合が多い |
| 運用コスト | 小規模利用では低いが、大規模運用では高コストになる可能性 | 利用量に応じた従量課金制が多く、高額になる可能性 |
| メンテナンス | 自社でモデルの更新や管理が必要 | サービス提供者が自動で実施 |
オンプレミスAIとの関連性
オンプレミスAIとは、企業が自社で管理するサーバーやデータセンター内にAIシステムを構築・運用する形態のことです。ローカル生成AIは、このオンプレミスAIの一種と位置づけられます。特に、個人のPCレベルから社内サーバーまで、幅広い規模の「ローカル環境」でAIを動かす形態を総称してローカル生成AIと呼ぶ傾向にあります。
大規模なサーバー群を必要とした従来のオンプレミスAIに比べ、ローカル生成AIはより手軽に始められるケースも含まれる点が大きな特徴です。例えば、特定の部署のPC数台で小規模にPoC(概念実証)を開始することもできます。
ローカル生成AIを導入する3つのメリット

ローカル生成AIの導入は、企業にセキュリティの強化、安定した動作、そして高いカスタマイズ性という3つの決定的なメリットをもたらします。これらはクラウド型サービスでは得難い利点であり、特に機密情報を扱う企業や独自の業務プロセスを持つ企業にとって重要な価値を持ちます。
高いセキュリティと情報漏洩リスクの低減
最大のメリットは、情報漏洩リスクを大幅に低減できる点です。ローカル生成AIは、入力したデータやAIとのやり取りが全て自社の管理下にあるPCやサーバー内で完結します。そのため、顧客情報や財務データ、研究開発情報といった機密性の高い情報が外部のサーバーに送信されることが一切ありません。(出典:中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き)
ただし、クラウド型AIでも、法人向けプランでは入力データがAIの学習に利用されない契約が標準となっています。ローカル環境は、適切な運用によりリスク低減が見込まれる一方で、内部の運用ミスやマルウェア感染などのリスクは残るため、総合的なセキュリティ対策が重要です。
ネットワークに依存しない安定した動作と高速応答
ローカル生成AIは、一度セットアップすればインターネット接続なしで運用できる場合が多いため、ネットワーク環境に左右されずに安定して動作します。例えば、通信環境が不安定な建設現場や、セキュリティポリシー上インターネットから遮断されたオフラインの工場、研究施設でも問題なく利用可能です。
また、処理が手元のPCで完結するため、データを外部サーバーとやり取りする時間がなく、応答速度(レイテンシ)が非常に速いという利点もあります。高性能なPCを用意すれば、クラウド型サービスよりも迅速に応答を得られる場合も多く、ストレスのない操作感を実現できるでしょう。
独自データによる自由度の高いカスタマイズ
自社の業務に完全に特化したAIを構築できる、極めて高いカスタマイズ性も大きな魅力です。ローカル生成AIでは、社内に蓄積された専門文書や過去の議事録、顧客との応対履歴といった独自のデータをAIモデルに追加学習(ファインチューニング)させることが容易です。
これにより、業界特有の専門用語を深く理解し、社内フォーマットに沿った文書を生成するなど、汎用的なクラウド型AIでは難しい、自社の業務に最適化された高精度なAIアシスタントを開発できます。このカスタマイズこそが、業務の自動化や品質向上を次のレベルへと引き上げる鍵となります。
ローカル生成AIの注意すべき3つのデメリット

ローカル生成AIは多くのメリットを提供する一方で、導入にはいくつかの課題も伴います。特に、高性能なハードウェアへの初期投資、環境構築と運用に必要な専門知識、そして継続的なメンテナンスの手間が主なデメリットとして挙げられます。これらを事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。
高性能なハードウェアへの初期投資コスト
ローカルで大規模言語モデルを快適に動作させるには、高性能なPCやサーバーが必要不可欠です。特に重要となるのが、AIの計算処理を担うGPU(Graphics Processing Unit)とそのVRAM(ビデオメモリ)容量です。モデルの規模が大きくなるほど、より多くのVRAMが要求されます。
小規模・断続的な利用ではランニングコストを抑えられますが、大規模運用(複数GPUの24時間稼働など)の場合は、ハードウェア購入費に加え、電力、冷却、管理のための人件費で高コストになる可能性があります。そのため、導入前には慎重なコスト試算が求められます。
環境構築と運用における専門知識の必要性
ローカル生成AIの導入は、専門的な技術知識が求められる点も大きなハードルです。必要なソフトウェアのインストール、Pythonなどのプログラミング言語やライブラリのバージョン管理、モデルのセットアップなど、環境構築には相応の技術スキルが必要になります。
また、運用開始後もトラブルシューティングやパフォーマンスの最適化など、継続的な管理が欠かせません。社内にこれらのスキルを持つ人材がいない場合、習得までに時間がかかったり、外部の専門家に支援を依頼したりする必要が生じるでしょう。
最新モデルへの追従やメンテナンスの手間
生成AIの技術は日進月歩で進化しており、次々と新しい、より高性能なモデルが公開されます。クラウド型サービスであれば、事業者が自動で最新モデルにアップデートしてくれますが、ローカル環境では自社で更新作業を行う必要があります。
新しいモデルを導入する際には、再度環境設定の見直しや互換性の確認が必要になる場合があります。また、セキュリティ上の脆弱性が発見された場合のアップデート対応なども自社の責任で行わなければならず、継続的なメンテナンス体制を構築しておくことが重要です。
【2026年最新】ローカルで使える主要な生成AIモデル・ツール5選

ローカル環境で利用できる生成AIは、特定の用途に特化したものから汎用的な対話モデルまで、多岐にわたる選択肢が存在します。ここでは、2026年時点で特に注目されている主要なモデルやツールを5つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の目的に合ったものを選ぶことが重要です。
1. 【画像生成】Stable Diffusion
Stable Diffusionは、テキストから高品質な画像を生成できるオープンソースのAIモデルです。(出典:Stable Diffusion Public Release)ローカル環境で動作させるためのインターフェース(WebUI)が複数存在し、初心者にも扱いやすいものから、より複雑なカスタマイズが可能なものまで様々です。ただし、生成物の著作権や学習データ由来のリスク、商用利用に関する制約がモデルや学習データにより異なるため、利用前に各モデルの利用規約・ライセンスと学習データ由来リスクを確認してください。
2. 【大規模言語モデル】Llama 3
Meta社が開発した独自ライセンス(Llama 3 Community License)で公開されている大規模言語モデル(LLM)です。オープンソース(OSIの定義)ではなく、オープンウエイトとして配布されています。(出典:Introducing Meta Llama 3)
80億(8B)と700億(70B)のパラメータサイズがあり、特に70Bモデルは多くのベンチマークで高い性能を示しています。商用利用が可能で、カスタマイズのベースモデルとして世界中の開発者に利用されています。日本語性能を向上させた派生モデルも登場しており、幅広い用途での活用が期待されています。
3. 【大規模言語モデル】Gemma
Googleが開発したオープンモデル(オープンウエイト)として公開されているLLMファミリーで、同社の高性能モデル「Gemini」と同じ技術を基に構築されています。こちらもオープンソース(OSIの定義)ではなく、Googleの独自利用規約(Gemma Terms of Use)の下で利用可能です。(出典:Use open models on Vertex AI)
20億(2B)から270億(27B)まで複数のサイズが提供されており、特に27Bモデルはそのサイズクラスで最高レベルの性能を発揮し、2倍以上の規模のモデルに匹敵するとされています。高い性能と効率性を両立しており、研究から商用アプリケーションまで幅広く利用可能です。
4. 【日本語特化モデル】ELYZA-japanese-Llama-2-7b
日本のAIベンチャーであるELYZA社が、Metaの「Llama 2」をベースに日本語データを追加学習させて開発したモデルです。(出典:ELYZA、日本語LLMの性能を測るベンチマークでトップクラスの性能を達成した70億パラメータのLLMを公開)
70億(7b)パラメータと軽量ながら、公開されている日本語LLMの中では最高水準の性能を持ち、一部のタスクではGPT-3.5に匹敵すると評価されています。商用利用も可能で、日本語の扱いに特化したローカルAIを構築したい場合に有力な選択肢となります。
5. 【統合実行環境】Ollama / LM Studio
これらは特定のAIモデルではなく、様々なローカルLLMを簡単に実行・管理するためのツールです。(出典:【ローカルLLM】各種実行環境(Ollama, LM Studio, etc)のまとめ)Ollamaはコマンドライン操作が基本の開発者向けツールですが、シンプルな操作でモデルをダウンロードし、すぐにチャットやAPI連携を試せます。LM Studioはグラフィカルなインターフェース(GUI)を備えており、Hugging Faceなどのサイトからモデルを検索・ダウンロードして直感的に実行できるため、非エンジニアでも扱いやすいのが特徴です。どちらも無料で利用でき、ローカルLLMを始める第一歩として最適です。
ローカル生成AIの主な活用事例
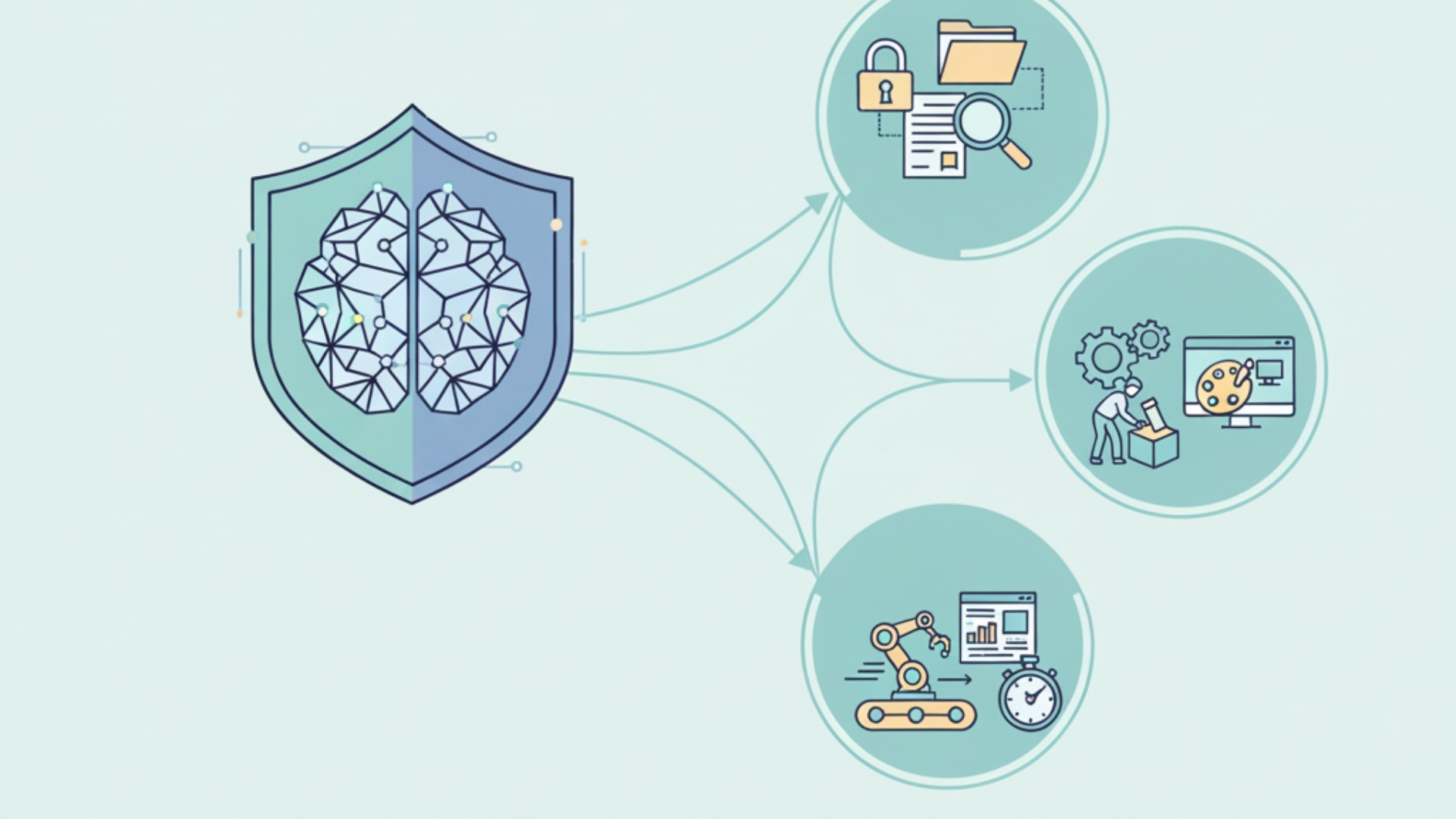
ローカル生成AIは、その高いセキュリティ性とカスタマイズ性を活かし、特に機密情報を扱う業務の自動化や効率化において大きな力を発揮します。外部に情報を出すことなく、社内データに基づいた高度な処理が可能になるため、これまでAIの導入が難しかった領域でも活用が着実に進んでいます。
社内文書の要約・翻訳・校正業務の自動化
企業内には、日々大量の文書が作成・蓄積されています。議事録や日報、技術仕様書、契約書案など、これらの文書をローカル生成AIに読み込ませることで、要約の自動作成、他言語への翻訳、誤字脱字のチェックといった作業を効率化できます。機密情報を含むこれらの文書を外部に出す必要がないため、情報漏洩のリスクを心配することなく、従業員は文書作成やレビューにかかる時間を大幅に削減できるのです。
機密情報を含むデータ分析とレポート作成
財務データ、人事情報、顧客の購買履歴といった機密性の高いデータを分析し、経営判断に役立つインサイトを抽出する業務にもローカル生成AIは有効です。例えば、売上データを分析して週次のレポートを自動生成したり、顧客からのフィードバックを解析して製品改善のポイントを抽出したりすることが可能です。全てのデータ処理が社内ネットワークで完結するため、安全にデータドリブンな意思決定を推進できます。
オフライン環境での社内向けチャットボット運用
社内の規定や業務マニュアル、過去の問い合わせ履歴などを学習させた社内向けチャットボットを構築する事例も増えています。従業員は、PCやスマートフォンから自然な言葉で質問するだけで、必要な情報をすぐに入手できるようになります。これをローカルで運用することにより、インターネットに接続できない工場や店舗でも利用可能なヘルプデスクとして機能させることができます。これにより、情報システム部門や総務部門への問い合わせ対応の工数を削減し、従業員の自己解決を促進します。
ローカル生成AIの環境構築を始める3ステップ
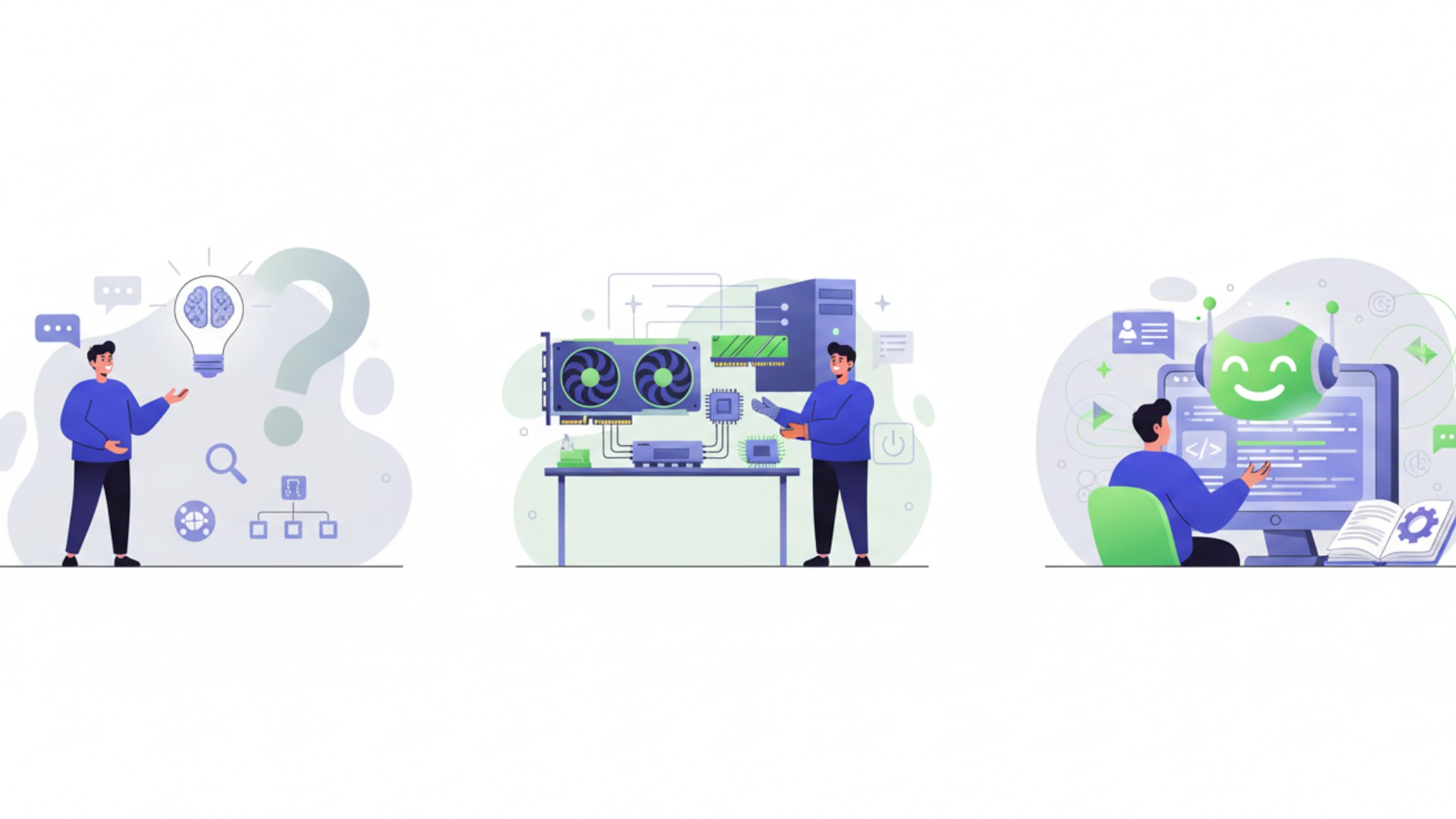
ローカル生成AIの導入は、クラウドサービスのようにアカウントを登録するだけでは完了しません。しかし、手順を正しく踏めば、過度に恐れる必要はありません。目的の明確化、ハードウェアの準備、そしてソフトウェアのインストールという3つのステップで進めることで、スムーズに環境を構築できます。
ステップ1:目的の明確化とモデルの選定
最初に、「ローカル生成AIを使って何を達成したいのか」という目的を具体的に定義します。目的によって、最適なAIモデルの種類や規模が変わってくるため、このステップが最も重要です。「社内文書の要約をしたい」のであれば言語モデル、「デザイン案を生成したい」のであれば画像生成モデルが必要になります。
目的が明確になったら、その要件を満たすモデルを選定します。日本語の処理能力、必要な性能、ライセンス(商用利用の可否)などを考慮し、Llama 3やELYZAモデル、Stable Diffusionといった選択肢の中から最適なものを選びましょう。
ステップ2:ハードウェア(PCスペック)の準備
次に、選定したモデルを動かすためのハードウェア、主にPCのスペックを確認・準備します。最も重要なのはGPUの性能、特にVRAM(ビデオメモリ)の容量です。動かしたいモデルが要求するVRAM容量を、使用するPCが満たしているかを確認してください。
入門レベルとしては、VRAM 12GB以上のGPU、メインメモリ(RAM) 16GB以上、高速なSSDストレージが一つの目安となります。スペックが不足している場合は、GPUの増設やPCの新調を検討する必要があります。Macの場合は、M1/M2/M3チップと大容量の統合メモリを搭載したモデルが適しています。
ステップ3:実行環境とモデルのインストール
ハードウェアの準備が整ったら、いよいよソフトウェアをインストールします。まず、OllamaやLM Studioといった統合実行環境ツールを公式サイトからダウンロードしてインストールしましょう。これらのツールを使えば、複雑なコマンド操作なしで目的のAIモデルを導入できます。
ツールのインストール後、その管理画面上からステップ1で選定したAIモデル(例:「Llama 3」)を検索し、ダウンロード・インストールを実行します。インストールが完了すれば、すぐに対話画面などでローカル生成AIを使い始めることが可能です。
ローカル生成AI導入で失敗しないためのポイント

ローカル生成AIの導入を成功させるためには、技術的な環境構築だけでなく、戦略的な視点が不可欠です。特に、費用対効果を慎重に見極めるためのスモールスタートと、AIを継続的に活用し続けるための運用体制の構築が失敗を避けるための重要なポイントとなります。
スモールスタートで費用対効果を検証する
全社的に大規模な導入をいきなり目指すのではなく、まずは特定の部署や限定的な業務から小さく始める「スモールスタート」が賢明です。これにより、高額なハードウェア投資を最小限に抑えながら、ローカル生成AIが自社の課題解決に本当に役立つのか、費用対効果(ROI)はどの程度見込めるのかを具体的に検証できます。
例えば、法務部で契約書のレビュー支援に試用してみる、あるいはマーケティング部で広告コピーの生成を試すなど、目的を絞ってPoC(概念実証)を行います。この小さな成功体験を社内で共有することが、本格展開に向けた理解と協力を得るための最も確実な方法です。
運用体制と人材育成の計画を立てる
AIは導入して終わりではなく、継続的に運用し、改善していく体制を整えることが成功の鍵を握ります。誰がモデルのメンテナンスやアップデートを担当するのか、利用する現場の従業員からの質問やトラブルにどう対応するのか、といった運用ルールをあらかじめ決めておく必要があります。
また、従業員がAIを効果的に使いこなせるようになるための研修や教育も欠かせません。AIに適切な指示を出す「プロンプトエンジニアリング」のスキルや、AIの得意・不得意を理解するリテラシーを向上させることで、導入効果を最大化できます。社内での人材育成が難しい場合は、私たちのような外部の研修サービスを活用することも有効な手段です。
AIのセキュアな活用と業務効率化ならAX CAMPの法人研修

ローカル生成AIの導入は、セキュリティ面で大きなメリットがある一方で、環境構築の技術的なハードルや、どの業務にどう活用すれば効果が出るのかという企画・推進の難しさが伴います。多くの企業が「導入方法がわからない」「専門知識を持つ人材がいない」「費用対効果が見えない」といった課題に直面し、AI活用の第一歩を踏み出せずにいます。
もし、あなたが自社でのAI導入をより確実かつスムーズに進めたいとお考えなら、AX CAMPの法人向けAI研修・伴走支援サービスが力になります。AX CAMPは、単なるツールの使い方を教える研修ではありません。貴社の具体的な業務課題をヒアリングし、ローカルAIとクラウドAIのどちらが最適かといった選定の段階から、実際の業務プロセスに組み込むための実践的なカリキュラムをお届けします。私たちの支援実績や提供内容、そして想定される効果の範囲について丁寧にご説明します。
「まずは何から始めれば良いのか知りたい」「自社のこの業務はAIで効率化できるのか相談したい」といった初期段階のご相談も歓迎です。専門家による無料相談を通じて、貴社に最適なAI活用のロードマップを描くお手伝いをします。より詳しいサービス内容や実績については、ぜひ無料相談をご活用ください。
まとめ:ローカル生成AIでセキュアなAI活用を実現しよう
本記事では、ローカル生成AIの基本からメリット・デメリット、具体的な導入ステップまでを解説しました。改めて、重要なポイントを振り返ります。
- ローカル生成AIとは:手元のPCや自社サーバーで動作するAI。データが外部に出ないため、セキュリティに利点がある。
- 主なメリット:高いセキュリティ、オフラインでの安定動作、独自データによる自由なカスタマイズ。
- 主なデメリット:高性能なハードウェアへの初期投資、環境構築・運用に関する専門知識の必要性。
- 導入のポイント:スモールスタートで費用対効果を検証し、運用体制と人材育成の計画を立てることが成功の鍵。
情報漏洩のリスクを懸念してAI導入を見送ってきた企業にとって、ローカル生成AIはセキュリティと業務効率化を両立させる強力な選択肢です。しかし、その導入と活用を成功させるには、技術的な知見と戦略的な計画が不可欠です。どのモデルを選び、どの業務に適用し、どのように社内に浸透させていくか、専門的な判断が求められる場面は少なくありません。
AX CAMPでは、こうした企業の課題に対し、専門家の知見と実践的な研修プログラムで応えます。貴社の状況に合わせた最適なAI導入プランの策定から、現場の従業員がAIを使いこなすためのスキル習得、そして成果創出までをワンストップで支援します。「AI導入で失敗したくない」「着実に成果を出したい」とお考えなら、まずは無料相談にお申し込みください。貴社のAI活用の可能性を一緒に考えていきましょう。