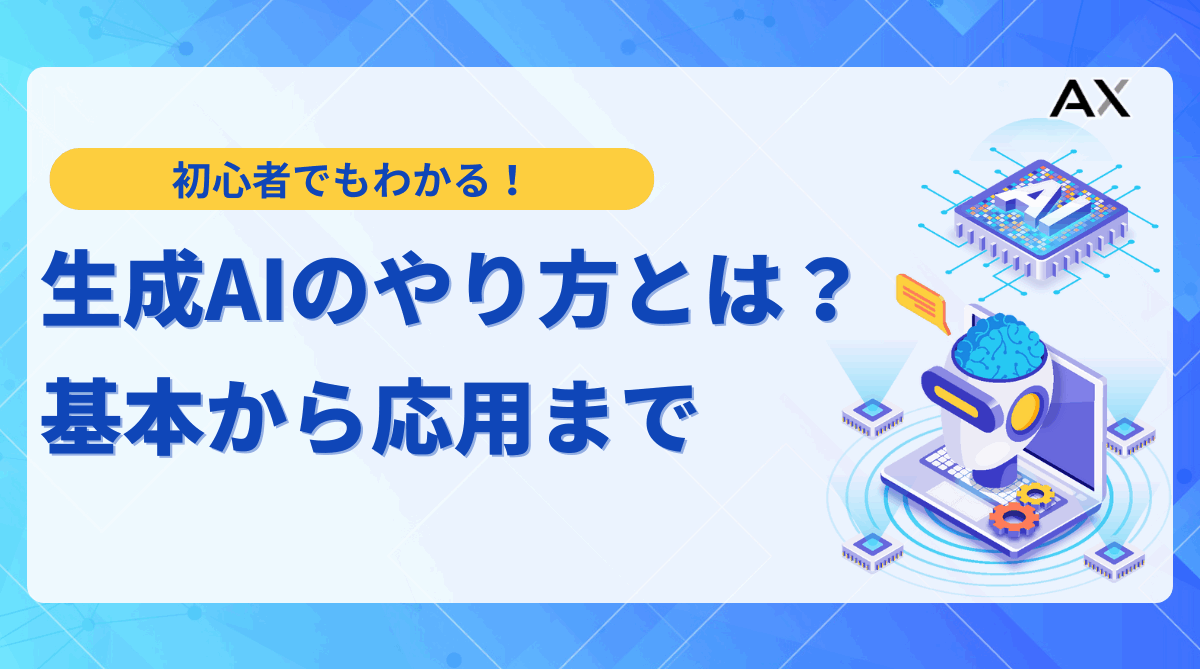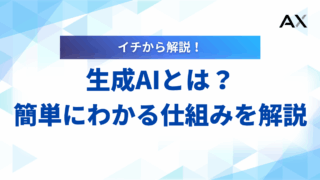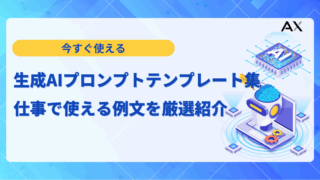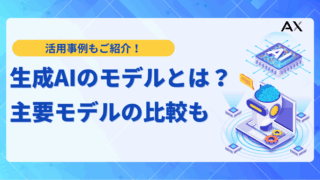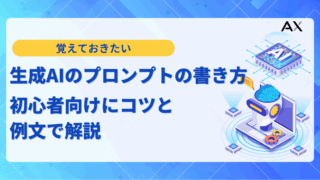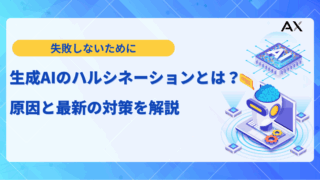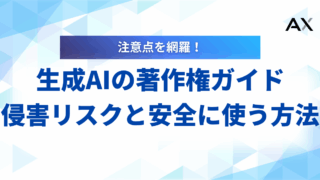「生成AIに興味があるけど、何から始めればいいかわからない」
「専門的で難しそう…」
と感じていませんか?生成AIは、文章作成からデザイン、動画制作まで、今やビジネスに欠かせないツールとなりつつあります。
この記事を読めば、初心者でも生成AIの基本から具体的な使い方、ビジネスでの活用事例までを体系的に理解し、すぐに実践できるようになります。生成AIを使いこなすことで、これまで数時間かかっていた作業が数分で完了するなど、業務効率を飛躍的に向上させることが可能です。さらに実践的なスキルを習得したい方のために、具体的な研修プログラムを紹介した資料もご用意しています。ぜひ最後までご覧いただき、生成AI活用の第一歩を踏み出してください。
生成AIとは?基本をわかりやすく解説

結論として、生成AI(ジェネレーティブAI)とは、学習済みのデータが持つ統計的なパターンを利用して、新しい組み合わせのコンテンツを創り出す技術のことです。ユーザーがテキストや画像で指示(プロンプト)を与えるだけで、AIがその意図を解釈し、文章、画像、音楽、動画といった多様な形式のデータを生成します。出力は訓練データの影響を受けるため、完全にゼロからの創造とは言えませんが、これまで人間にしかできなかった創造的な作業をAIが代行できるようになった画期的な技術として、多くの分野で注目されています。
この技術の登場により、業務の効率化や新しいアイデアの創出が、専門知識がない人でも手軽に行えるようになりました。次のセクションでは、この生成AIがどのようにして新しいコンテンツを生み出すのか、その仕組みについて掘り下げていきます。
基本的な仕組みと動作原理
生成AIは、「ディープラーニング(深層学習)」という技術を用いて、膨大なデータを学習することから始まります。この学習プロセスを通じて、データの中にあるパターンや関連性を抽出し、それらを組み合わせて新しいコンテンツを生成します。例えば、大量の猫の画像を学習したAIは、「猫らしさ」の特徴を理解し、実在しない猫の画像をゼロから描けるようになります。
代表的な生成モデルの原理は、生成対象によって異なります。ChatGPTなどに採用されている言語モデルは、与えられた指示に対し、次に来る単語の確率分布を基に最も自然な文章を生成します。一方、画像生成で主流の拡散モデルは、ノイズだらけの画像から段階的にノイズを除去していくことで、指示に沿った鮮明な画像を復元する仕組みです。
主な種類(テキスト、画像、音声、動画)
生成AIは、生成するコンテンツの種類によって、主に4つに分類されます。それぞれのAIは得意な分野が異なり、目的に応じて使い分けることが重要です。
- テキスト生成AI:ブログ記事やメールの作成、文章の要約、翻訳、アイデア出しなど、あらゆる文章作成作業を自動化します。
- 画像生成AI:キーワードや簡単なスケッチから、高品質なイラスト、写真、デザイン案などを生成します。資料の挿絵やWebサイトのビジュアル作成に活用できます。
- 音声・音楽生成AI:テキストを自然な人間の声で読み上げたり、特定の雰囲気やジャンルを指定してオリジナルのBGMを作成したりできます。
- 動画生成AI:テキストや画像をもとに、短いプロモーションビデオやSNS用の動画コンテンツを自動で生成します。
これらのAIツールを組み合わせることで、さらに複雑で創造的なコンテンツ制作も可能になります。次のセクションでは、従来のAIとの違いを明確にしていきましょう。
従来のAIとの決定的な違い
生成AIと従来のAIとの決定的な違いは、学習データを踏まえて「新しいコンテンツを自ら創造できるか否か」という点にあります。従来のAIは、与えられたデータの中から正解を見つけ出したり、データを分類・予測したりすることが主な役割でした。例えば、画像認識AIは「この画像に写っているのは猫か犬か」を判断しますが、新しい猫の画像を描くことはできません。
一方で、生成AIは学習したデータをもとに、新たなものを生成する作業が可能です。この能力により、単なる作業の自動化にとどまらず、人間の創造性を拡張し、新たなアイデアや表現を生み出すパートナーとしての役割が期待されています。
生成AIでできること【目的別】

生成AIは、その応用範囲の広さが大きな魅力です。文章作成のような日常的な業務から、デザインや動画制作といった専門的なクリエイティブ作業まで、アイデア次第で様々なビジネスシーンに応用できます。目的別にどのようなことが実現できるのかを理解することで、自社の課題解決に繋がる具体的な活用イメージを持つことができるでしょう。
ここでは、代表的な目的である「テキスト生成」「画像・イラスト生成」、そしてより専門的な「動画・音楽・コード生成」の3つの分野に分けて、具体的な活用例を紹介します。
テキスト生成:文章作成・要約・翻訳
テキスト生成AIは、ビジネスにおけるコミュニケーションや情報発信の効率を劇的に向上させます。最も身近で導入しやすい生成AIの一つと言えるでしょう。
- 文章作成:メールの返信文、ブログ記事、プレスリリース、SNSの投稿文など、様々な種類の文章を数秒で作成できます。
- 要約:長文のレポートや議事録、ウェブ記事などを短時間で要約し、重要なポイントを素早く把握できます。
- 翻訳:高精度な翻訳により、海外の文献調査やグローバルなコミュニケーションをスムーズにします。
- アイデア出し:新しい企画のブレインストーミングや、キャッチコピーの提案など、思考の壁を打ち破る手助けをします。
これらの機能を活用することで、情報収集や資料作成にかかる時間を大幅に短縮し、より戦略的な業務に集中する時間を生み出します。
画像・イラスト生成:デザイン・資料作成
画像生成AIは、専門的なデザインスキルがない人でも、高品質なビジュアルコンテンツを簡単に作成できるようにします。これにより、クリエイティブ制作のハードルが大きく下がりました。
- デザイン制作:ウェブサイトのバナー、広告クリエイティブ、SNS用の画像などを、テキストでイメージを伝えるだけで生成できます。
- 資料作成:プレゼンテーション資料や報告書に挿入するイラストやグラフのイメージを、内容に合わせて素早く作成できます。
- アイデアの視覚化:頭の中にある漠然としたイメージを具体化し、関係者との認識合わせをスムーズにします。
- 多様なスタイルの試作:写真風、水彩画風、アニメ風など、様々なスタイルのデザイン案を短時間で比較検討できます。
外注にかかっていたコストや時間を削減できるだけでなく、クリエイティブの試行錯誤を高速化できる点も大きなメリットです。
専門分野での活用(動画・音楽・コード生成)
生成AIの活用は、テキストや画像にとどまりません。より専門的な知識や技術が必要だった分野でも、その能力を発揮し始めています。
- 動画生成:テキストの指示から、製品紹介ビデオや広告用の短い動画を自動で生成します。既存の動画の背景を変えたり、スタイルを変換したりといった編集も可能です。
- 音楽生成:動画のBGMやアプリケーションの効果音など、用途や雰囲気を指定するだけでオリジナルの楽曲を生成します。
- コード生成:プログラミングの知識が浅い人でも、必要な機能を伝えることで、簡単なプログラムやスクリプトを自動で生成できます。特にコード生成は既に多くの開発チームで補助的に使われ、継続的インテグレーション(CI)やテスト、セキュリティレビューなどを組み合わせて運用されています。
これらの専門分野での活用は急速に進んでおり、将来的にはコンテンツ制作やシステム開発のあり方を大きく変える可能性を秘めています。
【初心者向け】生成AIの基本的なやり方3ステップ

生成AIは、決して専門家だけのものではありません。基本的な3つのステップを踏むだけで、誰でも簡単に使い始めることができます。難しく考えずに、まずは気軽に試してみることが、活用の第一歩です。これから紹介する手順に沿って、あなたも生成AIの世界を体験してみましょう。
このプロセスを理解すれば、様々なAIツールに応用が利くようになります。
STEP1:目的と利用ツールの選定
まず、「何のために生成AIを使いたいのか」という目的を明確にします。目的がはっきりすることで、数あるツールの中から最適なものを選ぶことができます。例えば、「ブログ記事を書きたい」ならテキスト生成AI、「プレゼン資料のイラストが欲しい」なら画像生成AI、といった具合です。
目的が決まったら、それに合ったツールを選びます。世の中には無料で始められるツールも多く存在するため、まずはそれらを試してみるのがおすすめです。ツールを選ぶ際は、日本語に対応しているか、操作が直感的かといった点に加え、ビジネスで使うなら「学習データの利用規約、商用利用の許諾範囲、再配布権利、API利用時のデータ保護条項」などを確認することが重要です。
STEP2:アカウント登録と基本設定
利用したいツールが決まったら、公式サイトにアクセスしてアカウントを登録します。多くの場合、メールアドレスやGoogle、Microsoftなどの既存アカウントで簡単に登録できます。登録後、サービスによっては簡単なチュートリアルが表示されることもあるので、それに従って基本的な操作方法を把握しましょう。
有料プランがあるツールでも、多くは無料のトライアル期間や機能制限付きの無料プランが用意されています。まずは無料プランで使い勝手を試し、本格的に活用したくなったら有料プランへのアップグレードを検討するのが賢明です。
STEP3:プロンプト(指示文)の入力と生成
アカウント登録が完了したら、いよいよコンテンツを生成します。生成AIへの指示は「プロンプト」と呼ばれるテキスト入力によって行います。このプロンプトの質が、生成されるコンテンツの質を大きく左右します。
最初は難しく考えず、「笑顔の猫のイラスト」「AIのメリットについてのブログ記事案」のように、シンプルにやってみたいことを入力してみましょう。出力された結果を見て、さらに「もっとリアルな写真風にして」「ビジネス向けの口調で」といったように指示を追加・修正していくことで、徐々に理想の生成物に近づけていくことができます。この試行錯誤のプロセス自体が、生成AIを使いこなすための最も効果的なトレーニングになります。
【種類別】主要な生成AIツールの使い方
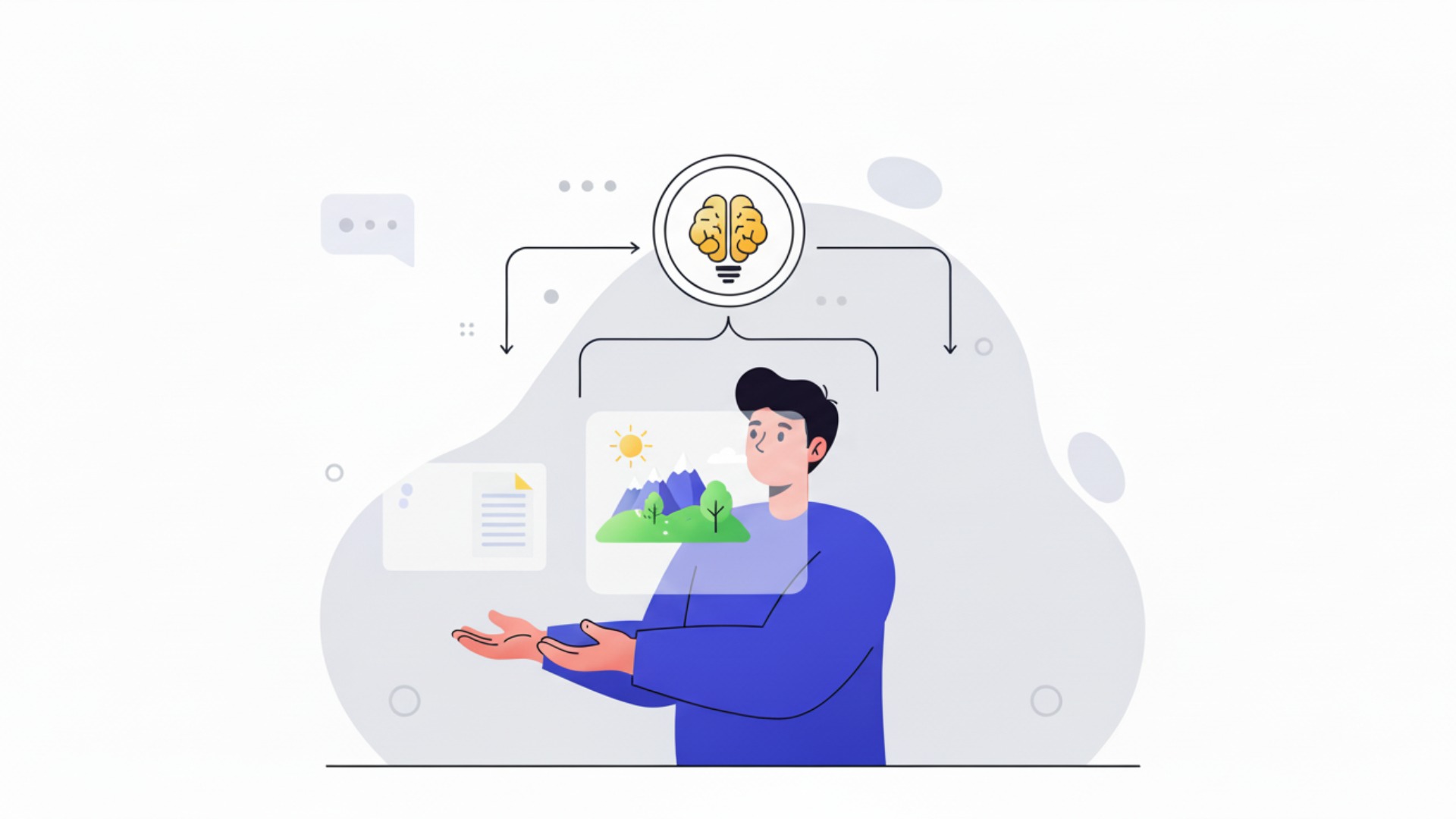
生成AIツールは種類ごとに特長があり、基本的な使い方も異なります。ここでは、代表的な「テキスト生成」「画像生成」「動画生成」の3つの分野で、特に広く使われているツールの基本的な使い方を紹介します。これらの使い方をマスターすれば、他の多くのツールにも応用が利くようになります。
それぞれのツールのインターフェースに慣れ、得意なこと・不得意なことを理解することが、効果的な活用の鍵となります。
テキスト生成AI(ChatGPT, Claude)の使い方
ChatGPTやClaudeなどのテキスト生成AIは、対話形式のインターフェースが特徴です。
- ログイン:公式サイトにアクセスし、アカウントでログインします。
- プロンプト入力:画面下部にある入力ボックスに、質問や依頼したい内容をテキストで入力します。例えば、「新商品のプレスリリースの構成案を3パターン考えてください」のように入力します。
- 生成と対話:AIが回答を生成します。その回答に対して、さらに「もっとフォーマルな表現にして」「ターゲットを若者向けに変えて」といった追加の指示を出すことで、内容をブラッシュアップしていくことができます。
会話を続けるように指示を重ねることで、AIの思考を誘導し、より精度の高い文章を生成させることが可能です。
画像生成AI(Midjourney, Stable Diffusion)の使い方
MidjourneyやStable Diffusionなどの画像生成AIは、テキストで表現したイメージをビジュアル化するツールです。
- プラットフォームへの参加:Midjourneyはコミュニケーションツール「Discord」上で利用します。Stable Diffusionはオープンソースの生成モデルであり、自身のPCにインストールして動かす(ローカル実行)ほか、クラウドサービス(Stability AI社のDreamStudioなど)や各種アプリケーションを通じて利用可能です。
- プロンプト入力:専用の入力欄に、生成したい画像のイメージを英語の単語や文章で入力します。「a photorealistic image of a cat wearing sunglasses, studio lighting(サングラスをかけた猫の写真のようにリアルな画像、スタジオ照明)」のように、具体的な情景や画風、品質に関するキーワードを入れるのがコツです。
- 画像の生成と選択:AIが複数の画像案を生成します。その中から気に入ったものを選び、さらに高解像度化したり、バリエーションを生成したりすることができます。
どのような単語(プロンプト)を使えばイメージに近い画像が生成されるか、コミュニティで共有されている作例を参考に試行錯誤するのが上達への近道です。
動画生成AI(Sora, Runway)の使い方
OpenAIのSoraやRunwayなどの動画生成AIは、テキストや画像から動画を創り出す最先端のツールです。(出典:Sora)
- ログインとモード選択:公式サイトにログインし、「Text to Video(テキストから動画へ)」や「Image to Video(画像から動画へ)」など、目的に合った生成モードを選択します。
- プロンプト入力または画像アップロード:テキストモードの場合は、生成したい動画のシーンを文章で詳しく記述します。「A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage.(ネオンが輝く東京の街を、おしゃれな女性が歩いている)」のように入力します。画像モードの場合は、動かしたい画像をアップロードし、動きの指示を追加します。
- 生成と調整:AIが数秒から数十秒の動画クリップを生成します。生成された動画の長さやスタイル、カメラワークなどを、追加のプロンプトや設定で調整することができます。
動画生成AIはまだ発展途上の技術ですが、簡単な操作で印象的な映像コンテンツを作成できるポテンシャルを秘めています。
【2026年版】目的別おすすめ生成AIツール7選

数多くの生成AIツールの中から、自社の目的に合った最適なものを選ぶのは簡単ではありません。ここでは、2025年9月時点の情報に基づき、特に評価が高く、様々なビジネスシーンで活用できる代表的なツールを7つ厳選しました。それぞれのツールの強みと主な用途を理解し、ツール選定の参考にしてください。
無料プランやトライアルが提供されているものも多いので、まずは実際に試してみることをお勧めします。
1. GPT-5(テキスト・対話・マルチモーダル)
OpenAIが開発したGPT-5は、非常に高度な対話能力と文章生成能力を持つ大規模言語モデルです。自然で論理的な文章作成はもちろん、プログラミングコードの生成、データ分析、さらには画像の内容を理解して対話するなど、マルチモーダルな能力も備えています。ビジネス文書の作成から専門的なリサーチ、アイデア出しまで、あらゆる知的生産活動をサポートする汎用性の高さが最大の強みです。(出典:Introducing GPT-5)
2. Claude Opus 4.1(長文読解・コーディング)
Anthropic社が開発したClaude Opus 4.1は、特に長文の読解・要約能力とコーディング性能に定評があります。最大200Kトークン(およそ15万語相当)のコンテキストを一度に扱うことができ、長大な文書を読み込みながら質疑応答や要約を高精度に行えます。契約書や研究論文のレビュー、複雑な仕様書に基づいたコーディング支援など、専門的で情報量の多いタスクで真価を発揮するモデルです。(出典:Meet Claude Opus 4.1)
3. Midjourney(高品質な画像生成)
Midjourneyは、芸術的で高品質な画像を生成することに特化したAIツールです。特に、写実的な表現や独創的なアートスタイルの生成に優れており、広告クリエイティブやコンセプトアート、Webデザインなどの分野でプロのクリエイターからも高い評価を得ています。Discordというチャットツール上で利用するのが特徴で、簡単なテキストプロンプトから、見る人を惹きつける魅力的なビジュアルを創り出せます。
4. Stable Diffusion 3(オープンソースで高機能な画像生成)
Stability AIが開発したStable Diffusion 3は、オープンソースであることが最大の特徴の画像生成AIです。 これにより、ユーザーはモデルを自由にカスタマイズしたり、自社のPCやサーバー上で実行したりできます。生成される画像の品質も非常に高く、特にプロンプトへの忠実性や、画像内に正確な文字を描写する能力が向上しています。(出典:Stable Diffusion 3)
5. Adobe Firefly(商用利用に強い画像生成)
Adobe Fireflyは、クリエイティブツールで有名なAdobe社が開発した画像生成AIです。Adobeは、Adobe Stock、オープンライセンスのコンテンツ、パブリックドメインなど権利がクリアなデータを学習に使用しており、商用利用の安全性を考慮して設計されていると説明しています。 ただし、生成物が既存作品と偶然類似するケースや各国の著作権法に基づくリスクは依然として存在するため、商用利用時は利用規約の確認とケースごとのリスク評価を行うべきです。(出典:Adobe Firefly)
6. Sora(高品質な動画生成)
OpenAIが開発したSoraは、テキストからリアルな動画を生成できるAIモデルとして注目されています。 プロンプトで指示された情景を正確に理解し、物理法則にもある程度従った、一貫性のある動画を生成できるとされています。広告や映画のプリビジュアライゼーション(事前視覚化)、製品デモなど、これまで多大なコストと時間がかかっていた動画制作のプロセスを根本から変える可能性を秘めています。(出典:Sora)
7. Microsoft Copilot(ビジネスユース・Office連携)
Microsoft Copilotは、同社の検索エンジンやOS、そしてWord、Excel、PowerPointといったMicrosoft 365アプリに統合された生成AI機能です。最新のWeb情報にアクセスしながら回答を生成できるほか、日常的に使用するビジネスツール上で、メールの下書き作成、会議内容の要約、プレゼン資料の自動生成などをシームレスに行えます。既存の業務フローを大きく変えることなく、生産性を向上させたいビジネスパーソンにとって最も身近で強力なツールの一つです。
生成AIの精度を高めるプロンプトのコツ

生成AIから質の高いアウトプットを引き出すためには、「プロンプト」と呼ばれる指示文の作り方が極めて重要です。AIは指示された内容を忠実に実行しようとしますが、指示が曖昧であれば、期待外れの回答が返ってくることも少なくありません。逆に、少しの工夫でAIの性能を最大限に引き出すことができます。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる、生成AIの精度を高めるための基本的な2つのコツを紹介します。
具体的で明確な指示を出す(役割・形式・5W1H)
AIに意図を正確に伝えるためには、プロンプトをできるだけ具体的かつ明確にすることが基本です。以下の要素を盛り込むことで、アウトプットの質が格段に向上します。
- 役割を与える:「あなたはプロのマーケターです」「あなたは経験豊富な編集者です」のように役割を指定することで、その立場にふさわしい専門的な視点や口調で回答を生成させることができます。
- 形式を指定する:「箇条書きで」「表形式で」「ブログ記事の形式で」など、希望するアウトプットの形式を明確に指示します。これにより、後工程での編集作業を大幅に削減できます。
- 5W1Hを意識する:「誰が(Who)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」をプロンプトに含めることで、背景情報や文脈がAIに伝わり、より的確な回答が得られます。
例えば、「AIについて教えて」という曖昧な指示ではなく、「あなたはITコンサルタントとして、中小企業の経営者(Who)向けに、明日(When)の社内会議(Where)で使うための生成AIのメリット(What)を、導入によるコスト削減の観点(Why)から、専門用語を使わずに箇条書き(How)で3つ説明してください」と指示することで、望む結果に大きく近づきます。
参考例を提示して精度を上げる(Few-shotプロンプティング)
より高度なテクニックとして、「Few-shotプロンプティング」という手法があります。これは、AIに回答の具体例をいくつか提示することで、出力のフォーマットや文体を学習させる方法です。特に、特定の形式に沿った文章を生成させたい場合に非常に有効な、AIの性能を引き出すための代表的な手法の一つです。
例えば、顧客からの問い合わせメールに対する返信文を作成させたい場合、以下のようにプロンプトを設計します。
【プロンプトの例】
以下の例のように、顧客からの問い合わせに返信してください。
例1)
問い合わせ:「製品Aの在庫はありますか?」
回答:「お問い合わせありがとうございます。製品Aは現在在庫がございます。ご注文後、2〜3営業日でお届け可能です。」
例2)
問い合わせ:「セミナーBの申し込み方法を教えてください。」
回答:「お問い合わせありがとうございます。セミナーBは、こちらのURLからお申し込みいただけます。[URLを記載]」
—
本番の問い合わせ:
「資料Cを送っていただけますか?」
このように例を示すことで、AIは「丁寧な挨拶から始める」「簡潔に回答する」といった暗黙のルールを理解し、それに沿った質の高い回答を生成できるようになります。
ビジネス活用を加速させる生成AIの導入事例

生成AIは、理論だけでなく、すでに多くの企業で具体的な成果を上げています。特に、これまで時間やコストがかかっていたクリエイティブ制作や情報発信業務において、生産性向上を実現した事例が次々と生まれています。ここでは、AX CAMPの支援を通じて成果を上げた企業の事例を3つ紹介します。
これらの事例から、自社で生成AIをどのように活用できるかのヒントを得ることができるでしょう。(個社の事例であり、成果は使用方法や環境に依存します)
LP制作コストと時間を大幅削減した株式会社グラシズの事例
株式会社グラシズ様は、ランディングページ(LP)のライティング業務に課題を抱えていました。従来、外注に頼っていたため、1本あたり10万円のコストと3営業日の制作時間がかかっていました。AX CAMPのプログラムを通じて生成AIの活用法を習得した結果、これらの作業を内製化。外注費は0円になり、制作時間もわずか2時間へと約93%の大幅な短縮に成功しました。これにより、コスト削減と迅速なマーケティング施策の展開を両立させています。(出典:【AX CAMP導入事例】LP制作時間を93%削減し、外注費0円を達成した株式会社グラシズ様の軌跡)
原稿執筆時間を大幅に削減したRoute66株式会社の事例
Route66株式会社様では、記事コンテンツの原稿執筆が大きな負担となっていました。1本の記事を執筆するのに、従来は24時間もの時間を要していました。生成AI、特に文章生成ツールを業務フローに組み込むことで、この執筆時間をわずか10秒にまで短縮することに成功しました。これは99.99%以上の時間削減に相当します。創出された時間を企画や分析といった、より付加価値の高い業務に振り分けることで、コンテンツの質と量の両方を向上させています。(出典:【AX CAMP導入事例】原稿執筆24時間がわずか10秒に!Route66株式会社様のメディア運営革命)
SNS運用作業を66%削減したC社の事例
ある企業(C社)では、SNSアカウントの運用、特に投稿コンテンツの企画と作成に毎日多くの時間を費やしていました。1日あたり3時間かかっていた作業が、生成AIの活用により1時間に短縮されました。これは約66%の作業時間削減です。AIに投稿のアイデア出しや下書き作成を任せることで、担当者はコンテンツの質を高めるための最終調整やユーザーとのコミュニケーションに集中できるようになりました。結果として、作業時間を削減しながらも、月間1,000万インプレッションを達成するなど、運用成果の向上にも繋がっています。(出典:【AX CAMP導入事例】SNS運用時間を66%削減し、月間1000万impを達成したC社のAI活用術)
生成AIを利用する際の注意点と法的リスク

生成AIは非常に強力なツールですが、その利用にはいくつかの注意点と潜在的なリスクが伴います。特にビジネスで活用する際には、これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。何も知らずに利用すると、企業の信頼を損なったり、法的な問題に発展したりする可能性もゼロではありません。
ここでは、特に注意すべき「ハルシネーション」と「著作権・情報漏洩」の2つのリスクについて解説します。
ハルシネーション(誤情報)への対策
ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。AIは学習データにない情報や、データの関連性を誤って解釈した場合に、架空の内容を作り出すことがあります。例えば、存在しない判例を引用したり、歴史上の出来事を間違って説明したりするケースが報告されています。
この対策として最も重要なのは、生成された情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行うことです。特に、統計データ、専門的な情報、固有名詞などが含まれる場合は、信頼できる情報源(公式サイトや公的機関の発表など)で裏付けを取る習慣が不可欠です。また、AIに回答の根拠となる情報源を尋ねることも、ハルシネーションのリスクを低減する上で有効な手段です。
著作権侵害と情報漏洩のリスク
生成AIの利用には、法的なリスクも伴います。特に注意が必要なのが著作権と情報漏洩です。
著作権侵害:生成AIが学習データに含まれる既存の著作物と酷似したコンテンツを生成してしまう可能性があります。 これを気づかずに公開・商用利用した場合、著作権侵害にあたるリスクがあります。対策としては、Adobe Fireflyのように学習データの透明性が高く商用利用を想定したツールを選ぶことや、生成物が既存の作品と類似していないかを確認するプロセスが重要です。(出典:Adobe Firefly)
情報漏洩:利用するサービスやプランによっては、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があります。そのため、企業の機密情報や個人情報をプロンプトとして入力する際は、データ利用ポリシーを必ず確認する必要があります。多くのサービスでは、法人向けの有料プランやAPI経由の利用において、入力データを学習に用いない設定が提供されています。 社内で生成AIを利用する際は、入力してはいけない情報に関する明確なガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することが不可欠です。
生成AIのやり方に関するよくある質問

生成AIをこれから始めようとする方々から、よく寄せられる質問がいくつかあります。ここでは、特に多い3つの質問、「無料での利用」「商用利用の可否」「スマートフォンでの利用」について、簡潔にお答えします。これらの疑問を解消し、安心して生成AIの活用をスタートさせましょう。
無料で使える生成AIはありますか?
はい、無料で利用できる生成AIツールは多数存在します。多くの主要なサービス、例えばChatGPT、Gemini、Microsoft Copilotなどは、機能や利用回数に一部制限があるものの、無料で始められるプランを提供しています。 画像生成AIにおいても、Stable Diffusionのようにオープンソースで原則無料のものや、無料クレジットが付与されるサービスがあります。(出典:無料で使える生成AI(ジェネレーティブAI)とは?)
これらの無料ツールは、生成AIの基本的な性能を試したり、個人的な趣味の範囲で楽しんだりするには十分です。まずは無料プランで様々なツールを試し、自分の目的に最も合ったものを見つけるのが良いでしょう。
生成した画像や文章は商用利用できますか?
商用利用の可否は、利用するツールの利用規約によって異なります。そのため、ビジネスで利用する前には必ず各サービスの規約を確認することが不可欠です。 一般的に、無料プランでは商用利用が禁止または制限されていることが多いです。一方で、有料プランに加入することで商用利用が許可されるサービスが多数あります。また、Adobe Fireflyのように、学習データの権利関係がクリアで、商用利用を前提として設計されているツールもあります。 著作権トラブルを避けるためにも、特にビジネス用途ではライセンス条件が明確なツールを選択することが重要です。
スマホアプリでも生成AIは使えますか?
はい、多くの生成AIツールがスマートフォン向けの公式アプリを提供しており、手軽に利用できます。ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilotといった主要なテキスト生成AIは、iOSとAndroidの両方でアプリがリリースされています。また、CanvaやPicsartなど、画像生成機能を搭載したデザインアプリも多数存在します。
スマホアプリを使えば、移動中や外出先でもアイデアを手軽に形にしたり、急な資料作成のサポートを受けたりすることが可能です。PC版と機能がほぼ同じものも多く、いつでもどこでも生成AIのパワーを活用できるため、ビジネスの機動力が一層高まります。
実践的なスキルを習得するならAX CAMP

生成AIの基本的なやり方を理解した上で、次に重要になるのが「いかにしてビジネスの現場で成果に繋げるか」という実践的なスキルです。この記事で紹介したようなツールの使い方やプロンプトのコツは、あくまでスタートラインに過ぎません。本当に業務を効率化し、新たな価値を創造するためには、自社の課題に合わせた具体的な活用シナリオを描き、実行する能力が不可欠です。
しかし、「どのツールを自社のどの業務に適用すれば効果が最大化するのか」「社員がAIを使いこなせるようにするには、どのような教育が必要か」といった課題に直面する企業は少なくありません。ツールの導入だけで終わってしまい、思うような成果が出ないケースも散見されます。
私たち株式会社AXが提供する「AX CAMP」は、そのような課題を解決するために設計された実践型の法人向けAI研修・伴走支援サービスです。単なるツールの使い方を教えるのではなく、貴社の具体的な業務内容や課題をヒアリングした上で、実務に直結するカリキュラムをオーダーメイドで設計します。経験豊富な専門家が講師となり、現場での活用を見据えたノウハウを提供。研修で学んだ内容は、受講者のスキルや業務環境に応じて実践でご活用いただけますが、成果には個人差がある点はご了承ください。研修後も継続的な伴走サポートを通じて、AI活用の定着化と成果創出を強力に後押しします。
「AI導入で失敗したくない」「社員のAIリテラシーを底上げし、組織全体の生産性を向上させたい」とお考えの決裁者・推進担当者様は、ぜひ一度、AX CAMPの詳細をご覧ください。貴社のAI活用を成功に導くための具体的な道筋をご提案します。
まとめ:生成AIのやり方をマスターして業務を効率化しよう
この記事では、生成AIの基本から具体的な使い方、ビジネスでの活用事例、そして利用上の注意点までを網羅的に解説しました。改めて、本記事の重要なポイントを振り返ります。
- 生成AIとは:データ内のパターンから学習し、文章や画像などの新しいコンテンツを生成するAI技術である。
- 基本的なやり方:目的を明確にし、ツールを選定、プロンプトを入力するという3ステップで誰でも簡単に始められる。
- 精度向上のコツ:「役割を与える」「具体的に指示する」「参考例を示す」といったプロンプトの工夫が、アウトプットの質を大きく左右する。
- ビジネス活用:LP制作や記事執筆、SNS運用など、事例によっては業務時間を大幅に削減するなど、多くの企業で成果が報告されている。
- 注意点:誤情報(ハルシネーション)のリスクを理解し、ファクトチェックを徹底すること、著作権や情報漏洩に配慮することが不可欠である。
生成AIを使いこなすスキルは、もはや一部の専門家だけのものではありません。これからのビジネスパーソンにとって必須の教養となりつつあります。今日からでも、まずは無料のツールに触れてみてください。そして、その可能性を実感した先で、より本格的な業務活用を目指すのであれば、専門家の支援を受けることが成功への最短ルートです。
AX CAMPでは、貴社の状況に合わせた最適なAI導入プランの策定から、社員一人ひとりがAIを使いこなすための実践的な研修まで、一気通貫でサポートします。「何から手をつければ良いかわからない」という段階からでも、具体的な成果創出まで伴走します。AIを活用して競合他社に差をつけ、組織全体の生産性を飛躍的に向上させたいとお考えなら、ぜひ一度、無料相談にお申し込みください。