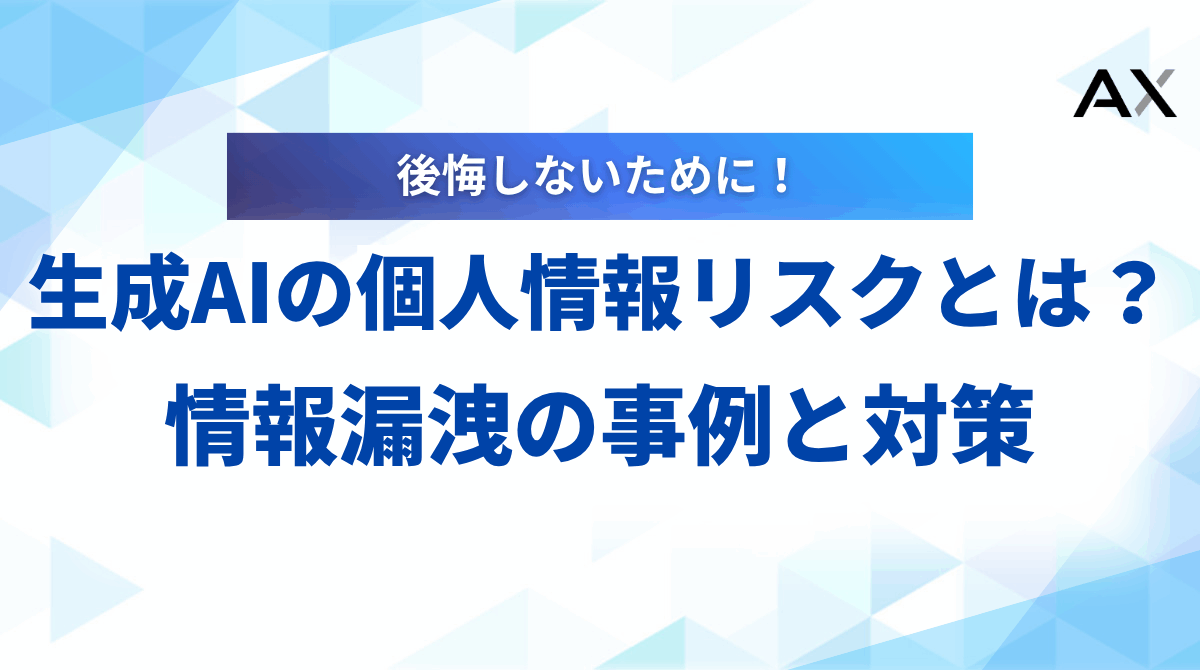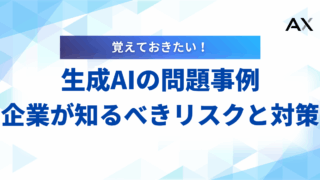「便利な生成AIを業務で活用したいが、個人情報や機密情報の漏洩が心配だ」
「どのような対策をすれば、安全に使えるのかわからない」
多くの企業担当者が、このような悩みを抱えています。生成AIは業務効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めていますが、その裏には情報漏洩という重大なリスクが潜んでいるのも事実です。適切な対策を講じなければ、企業の信用失墜や法的責任問題に発展しかねません。
しかし、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、生成AIは安全に活用できます。この記事では、生成AIに潜む個人情報漏洩の具体的なリスク、実際に発生した事故事例、そして企業が今すぐ実践すべき5つの対策を徹底的に解説します。さらに、個人情報保護法との関連性といった法的論点まで掘り下げていきます。
安全なAI活用を実現するための具体的なノウハウや、社内ガイドラインの策定方法をまとめた資料もご用意していますので、ぜひご活用ください。
記事:【AI導入しないことが経営リスクになる時代】先行企業が手にした圧倒的な競争優位とは?
生成AIと個人情報:なぜ今、対策が急務なのか?
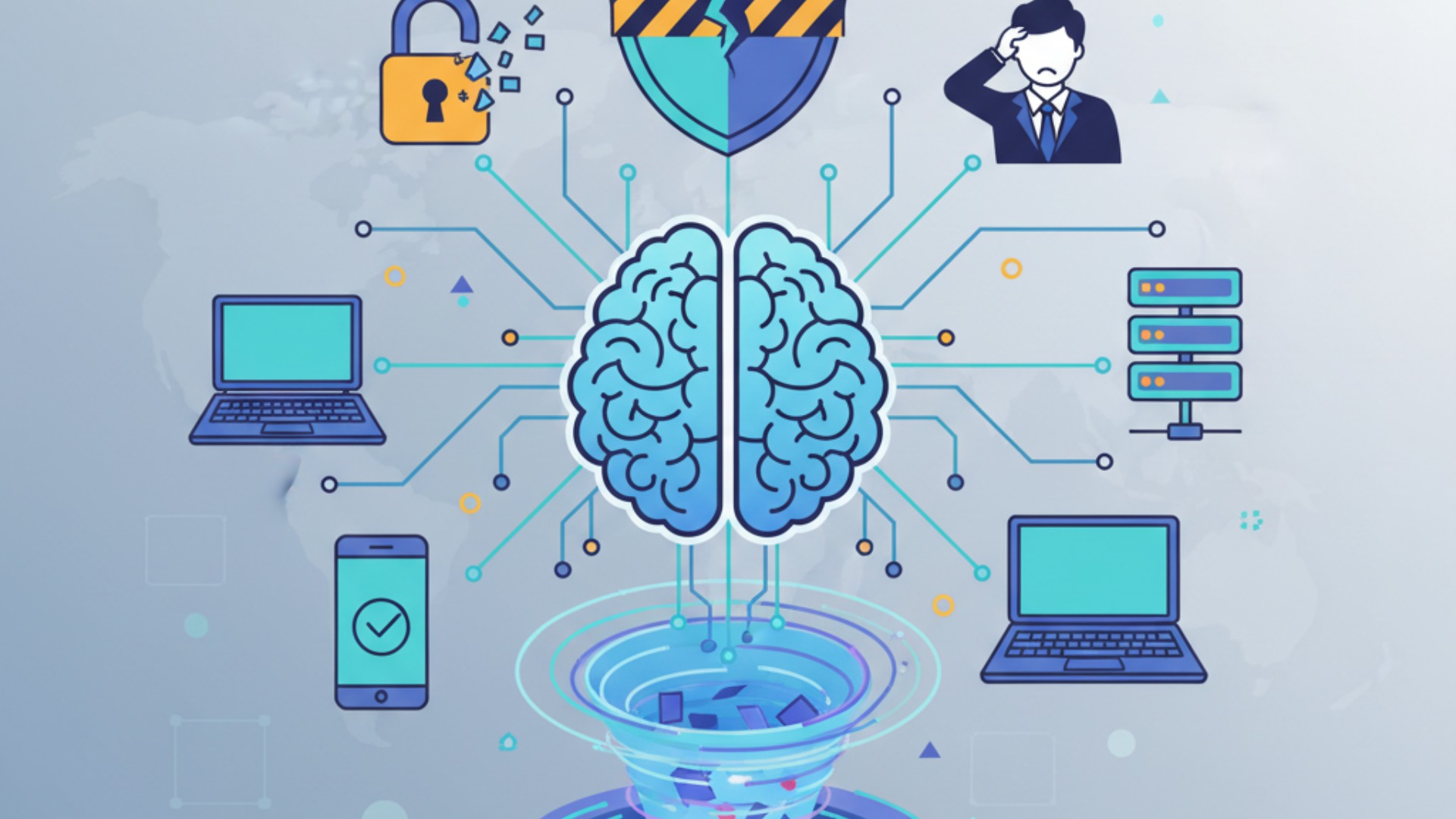
生成AIに関する個人情報漏洩対策が急務となっている背景には、ビジネスにおけるAI利用の急速な拡大と、それに伴う新たなセキュリティリスクの増大があります。従来の対策だけでは防ぎきれない脅威が出現しており、万が一インシデントが発生した場合の被害は計り知れません。
生成AIの技術は目覚ましいスピードで進化し、多くの企業が業務効率化や新たなサービス開発のために導入を進めています。市場規模も拡大を続け、ビジネスシーンでの活用はもはや当たり前の光景になりつつあります。しかしその一方で、従業員が個人や会社の機密情報を安易に入力してしまい、情報が漏洩するリスクが現実のものとなっているのです。
一度漏洩した情報は完全に取り戻すことが困難であり、企業の社会的信用の失墜、顧客からの損害賠償請求、そしてビジネス機会の損失など、経営に深刻なダメージを与える可能性があります。(出典:情報漏洩が企業に与える損害とは?発生原因や必要な対策を解説) そのため、技術の恩恵を最大限に享受しつつ、リスクを最小限に抑えるための対策を早急に講じることが、すべての企業にとって不可欠な経営課題となっています。
生成AI利用時に潜む個人情報漏洩の3大リスク

生成AIの利用には、大きく分けて3つの個人情報漏洩リスクが存在します。それは「入力データ」「サービス提供者のシステム」「生成コンテンツ」に起因するものです。これらのリスクを正しく理解することが、効果的な対策の第一歩となります。
入力データが意図せずAIの学習に利用されるリスク
最も注意すべきリスクの一つが、ユーザーがプロンプト(指示文)として入力したデータが、AIモデルの学習に利用されてしまうケースです。多くの一般向け公開サービスでは、デフォルト設定で入力データが品質向上のために利用される規約になっています。(出典:Usage policies)
もし従業員が顧客の個人情報や社内の機密情報をプロンプトに入力した場合、その情報がAIの知識の一部となり、他のユーザーからの質問への回答として外部に出力されてしまう可能性があります。一方で、法人向けのプランではデータが学習に利用されない設定が可能な場合が多く、サービス選定時にはこの違いを理解することが重要です。
サービス提供者のシステム脆弱性による外部流出リスク
次に、生成AIサービスを提供する事業者側のシステムに起因するリスクが挙げられます。これは、事業者のサーバーがサイバー攻撃を受けたり、システムにバグや脆弱性が存在したりした場合に、預けられているデータが外部に流出する可能性を指します。
実際に、過去には大手生成AIサービスでシステムのバグが原因となり、一部ユーザーの氏名、メールアドレス、クレジットカード情報などが他のユーザーに表示されてしまうというインシデントが発生しました。(出典:ChatGPTで他人の会話履歴が一時表示される不具合。有料会員の個人情報流出も) クラウドサービスを利用する以上、提供者側のセキュリティ体制に依存するこの種のリスクは避けられず、サービス選定における重要な判断基準となります。
生成コンテンツに他者の個人情報が含まれるリスク
最後に、生成AIが作り出すコンテンツ自体に、他者の個人情報が含まれてしまうリスクも考慮しなければなりません。生成AIは、インターネット上の膨大な情報を含む学習データの中からパターンを学び、文章や画像を生成します。
その過程で、学習データに含まれていた個人情報や機密情報を「記憶」してしまい、生成物の中に意図せずそのまま出力してしまうことがあります。これにより、自社が個人情報を入力していなくても、結果的に他者の権利を侵害してしまう可能性があるため、生成されたコンテンツのチェックも重要になります。(出典:ChatGPTでまた個人情報流出、有料会員の一部に OpenAIが報告書を公開)
【2026年最新】生成AIによる情報漏洩の事故事例

生成AIによる情報漏洩は、もはや理論上のリスクではありません。国内外の有名企業で、実際に従業員の不注意やシステムの脆弱性を原因とするインシデントが複数報告されています。ここでは代表的な事例を紹介し、そこから得られる教訓を考えます。
海外事例(Samsung Electronics)
韓国のSamsung Electronicsでは、従業員が業務効率化のために生成AIを利用した結果、重大な情報漏洩を引き起こした事例が2023年に報告されました。具体的には、エンジニアが機密情報であるソースコードのエラー修正を依頼するためにプロンプトに入力したり、会議の内容を要約させるために議事録の全文を入力したりしたケースです。(出典:サムスン電子、ChatGPTの社内利用を禁止 機密情報漏洩で)
これらの行為により、外部に公開できないはずの半導体設備の計測データや新製品に関する情報がAIの学習データとしてサーバーに送信されてしまいました。このインシデントは、従業員の何気ない行動が企業の競争力を揺るがす情報漏洩につながる危険性を示しており、全社的なルール作りと教育の重要性を浮き彫りにしました。
海外でのChatGPT会話履歴漏洩インシデント
サービス提供者側の問題で情報漏洩が発生した事例もあります。2023年3月、ChatGPTにおいて、一部のユーザーに他人のチャット履歴のタイトルが表示されてしまうというバグが発生しました。このバグは現在修正されています。
さらにこのインシデントでは、有料プランであるChatGPT Plusの会員情報(氏名、メールアドレス、支払い情報など)の一部も、ごく短時間ですが他のユーザーから閲覧可能になっていたことが判明しています。(出典:ChatGPTでまた個人情報流出、有料会員の一部に OpenAIが報告書を公開) 利用者側でどれだけ注意していても、サービス提供者側の問題で情報が漏洩するリスクが存在することを示す教訓的な事例と言えるでしょう。
情報漏洩はなぜ起こる?生成AIの仕組みに潜む原因

生成AIによる情報漏洩の原因は、その技術の根幹である「大量データからの学習」という仕組みそのものに深く関わっています。AIがなぜ、そしてどのようにして情報を漏洩させてしまうのか、そのメカニズムを理解することが不可欠です。
生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)は、インターネット上のWebサイト、書籍、論文といった膨大なテキストデータを読み込み、単語や文のつながりのパターンを統計的に学習します。この学習プロセスによって、人間のように自然な文章を生成したり、質問に答えたりする能力を獲得するのです。
問題は、この学習データの中に個人情報や機密情報がもともと含まれている場合があることです。また、多くの一般向けサービスでは、ユーザーが入力したプロンプトも新たな学習データとして利用し、AIの性能向上に役立てています。(出典:Usage policies) つまり、ユーザーが入力した機密情報は、AIの知識の一部として吸収され、将来的に他の誰かへの回答として再利用される可能性があるのです。この「入力データが学習に使われる」という仕組みが、情報漏洩の最大のリスク要因となっています。
企業が実践すべき生成AIの個人情報漏洩対策5選

生成AIを安全に活用するためには、技術的な対策と組織的なルールの両面からアプローチすることが極めて重要です。ここでは、企業が今日からでも実践できる具体的な5つの漏洩対策を紹介します。
1. 社内利用ガイドラインの策定と周知徹底
まず最も重要なのが、全社共通の利用ルールを定めることです。具体的には、「顧客の個人情報」「未公開の財務情報」「開発中の製品情報」など、入力してはならない情報を明確に定義し、ガイドラインとして明文化します。そして、このガイドラインを全従業員に周知し、定期的な研修を通じて遵守を徹底させることが不可欠です。
2. 法人向け・高セキュリティなAIサービスの選定
一般消費者向けの無料サービスではなく、セキュリティが強化された法人向けプランを選択することが推奨されます。特に、入力したデータをAIの学習に利用しない(オプトアウト)設定が可能なサービスや、Microsoft Azure OpenAI Serviceのように閉域網で利用できるサービスを選ぶことで、情報漏洩リスクを大幅に低減できます。(出典:How your data is used to improve model performance)
3. 入力情報の匿名化・マスキング
どうしても個人情報に関連するデータを扱いたい場合は、入力前にデータを加工し、個人を特定できない状態にする「匿名化」や「マスキング」といった手法が有効です。例えば、氏名を「Aさん」、会社名を「B社」のように置き換えるだけでも、リスクを大きく減らせます。これを自動で行うツールを導入することも一つの選択肢です。
4. アクセス管理と利用状況のモニタリング
誰が、いつ、どのように生成AIを利用しているかを把握できる体制を整えることも重要です。法人向けサービスには、利用ログを管理・監視する機能が備わっているものがあります。これにより、ガイドラインに違反するような不適切な利用を早期に検知し、対処することが可能になります。
5. 定期的な従業員教育とリテラシー向上
生成AIを取り巻く技術やリスクは日々変化しています。そのため、一度ガイドラインを作成して終わりにするのではなく、最新の事故事例や新たな脅威について学ぶ機会を定期的に設け、従業員全体のAIリテラシーを継続的に向上させていくことが、長期的な安全確保につながります。
押さえておくべき生成AIと個人情報保護法の法的論点

生成AIの利用は、業務効率化の観点から非常に魅力的ですが、個人情報保護法をはじめとする法規制との関係を無視することはできません。特に「個人データの取得」「利用目的」「第三者提供」という3つの観点から、法的な論点を正しく理解しておく必要があります。
個人データの「取得」と「利用目的」の観点
企業が顧客の個人情報(氏名、連絡先など)を含むデータを生成AIのプロンプトに入力する行為は、個人情報保護法における「利用」にあたります。法律では、個人情報を利用する際は、あらかじめ特定し公表している「利用目的」の範囲内に限定しなければならないと定められています。
例えば、「顧客への商品発送のため」に取得した個人情報を、AIを使って「新たなマーケティング施策の立案」のために分析・入力する場合、目的外利用とみなされる可能性があります。生成AIを利用する目的が、当初本人に通知または公表した利用目的の範囲内であるかを、事前に必ず確認しなければなりません。
AI提供者への情報提供は「第三者提供」にあたるか
プロンプトに個人データを入力すると、そのデータはAIサービスを提供する事業者(例:OpenAI社)のサーバーに送信されます。(出典:ChatGPT) この行為が、法律上の「第三者提供」に該当するかが重要な論点です。
個人情報保護委員会は、AIサービス提供者がそのデータを応答結果の出力以外の目的(例:AIモデルの学習)で利用する場合、原則として本人の同意が必要な第三者提供にあたるとの見解を示しています。(出典:個人情報保護委員会 第263回委員会 資料) そのため、入力データを学習に利用しない設定が可能な法人向けサービスを選ぶか、利用規約で学習に利用しないことが明記されているサービスを選定することが、コンプライアンス上極めて重要になります。
生成AIと個人情報に関するFAQ

ここでは、生成AIの個人情報リスクに関して、企業担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 生成AIに入力した情報は完全に削除できますか?
A. サービスによりますが、一般向けの無料サービスでは一度入力・学習された情報を完全に削除することは困難です。情報がAIモデルの内部に取り込まれてしまうため、特定のユーザーの入力だけを後から分離・削除することは技術的に難しいとされています。一方で、法人向けの有料サービスの中には、入力データを学習に利用せず、一定期間後に自動的に削除するオプションを提供しているものもあります。(出典:How your data is used to improve model performance) 自社のセキュリティポリシーに合わせて、契約内容を十分に確認することが重要です。
Q. 業務で安全に使えるおすすめの生成AIサービスはありますか?
A. 特定のサービスを一つだけ推奨することは難しいですが、安全性を重視する場合の選定ポイントは明確です。第一に、入力したデータがAIの学習に使われない(オプトアウト可能)ことが明記されているサービスを選ぶべきです。第二に、データの送受信が暗号化されていることや、企業のセキュリティ基準を満たしていることを確認します。具体的には、Microsoftが提供する「Azure OpenAI Service」やGoogle Cloudの「Vertex AI」などは、セキュリティを重視する企業向けの代表的なサービスとして挙げられます。
Q. 社員が個人情報を入力してしまった場合、会社はどんな責任を負いますか?
A. 個人情報保護法に基づき、複数の重大な責任を負う可能性があります。例えば、個人情報保護委員会からの指導・勧告・命令の対象となり得ます。命令に違反した場合は罰則が科されることもあります。また、情報が漏洩した本人(顧客や従業員)からプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を起こされるリスクも考えられます。インシデントが公になれば、企業の社会的信用は大きく損なわれ、取引停止や顧客離れといった深刻なビジネス上の損害につながる可能性があります。(出典:情報漏洩が企業に与える損害とは?発生原因や必要な対策を解説)
安全なAI活用と業務効率化を両立するならAX CAMPの研修へ

生成AIの情報漏洩リスクを理解し、適切な対策を講じることは、もはや全ての企業にとって必須の課題です。(出典:ガートナー、データセキュリティのハイプ・サイクル:2024年) しかし、「何から手をつければいいのかわからない」「自社に合ったガイドラインの作り方が難しい」と感じる担当者の方も少なくないでしょう。技術的な知識だけでなく、法的な要件や組織的なルール作りなど、求められるスキルは多岐にわたります。
もし、体系的かつ実践的にAIのリスク管理と活用方法を学びたいのであれば、AX CAMPの法人向けAI研修をご検討ください。AX CAMPでは、単なるツールの使い方を教えるだけではありません。最新の事故事例を基にしたセキュリティリスク研修、各社の実情に合わせた社内利用ガイドラインの策定支援、そしてAIを安全に活用して業務を自動化・効率化するための具体的なスキル習得までを、一気通貫でサポートします。
実際にAX CAMPを導入いただいた企業様では、特定の定型原稿の執筆に要していた時間が24時間から10秒に短縮されたり、LP制作の外注費月10万円が内製化により0円になったりと、具体的な成果が生まれています。
専門家による伴走支援を通じて、従業員一人ひとりのAIリテラシーを向上させ、全社的なセキュリティレベルを引き上げることが可能です。自社だけで対策を進めることに不安を感じるなら、まずはAX CAMPが提供するサービスの詳細を資料でご覧ください。
まとめ:生成AIにおける個人情報リスクを理解し、安全な活用を目指そう
本記事では、生成AIの利用に伴う個人情報漏洩のリスク、その原因となる仕組み、実際の事故事例、そして企業が取るべき具体的な対策について解説しました。改めて、重要なポイントを以下にまとめます。
- 生成AIの情報漏洩リスクは現実の脅威:従業員の不注意な入力や、サービス提供者側のシステム障害により、実際に国内外で情報漏洩インシデントが発生しています。
- 3つの主要なリスク:漏洩は主に「入力データが学習に使われる」「システムの脆弱性」「生成物に他者の情報が含まれる」という3つの経路で発生します。
- 対策の鍵はルールとツール選定:社内ガイドラインの策定と徹底した従業員教育が不可欠です。同時に、入力データを学習に利用しない法人向けの高セキュリティなサービスを選ぶことが極めて重要です。
- 個人情報保護法への準拠:「利用目的」の範囲を遵守し、「第三者提供」にあたらないかを確認するなど、法的な要件をクリアする必要があります。
生成AIは、正しく使えば業務を劇的に効率化し、新たな価値を創造する強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、リスクを正確に理解し、管理することが大前提となります。この記事で紹介した対策を参考に、自社の状況に合わせた安全な利用体制を構築してください。
もし、ガイドライン策定や社員教育の進め方、具体的な業務へのAI導入について専門的なサポートが必要であれば、ぜひAX CAMPにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な研修プログラムをご提案し、安全かつ効果的なAI活用を全面的に支援します。