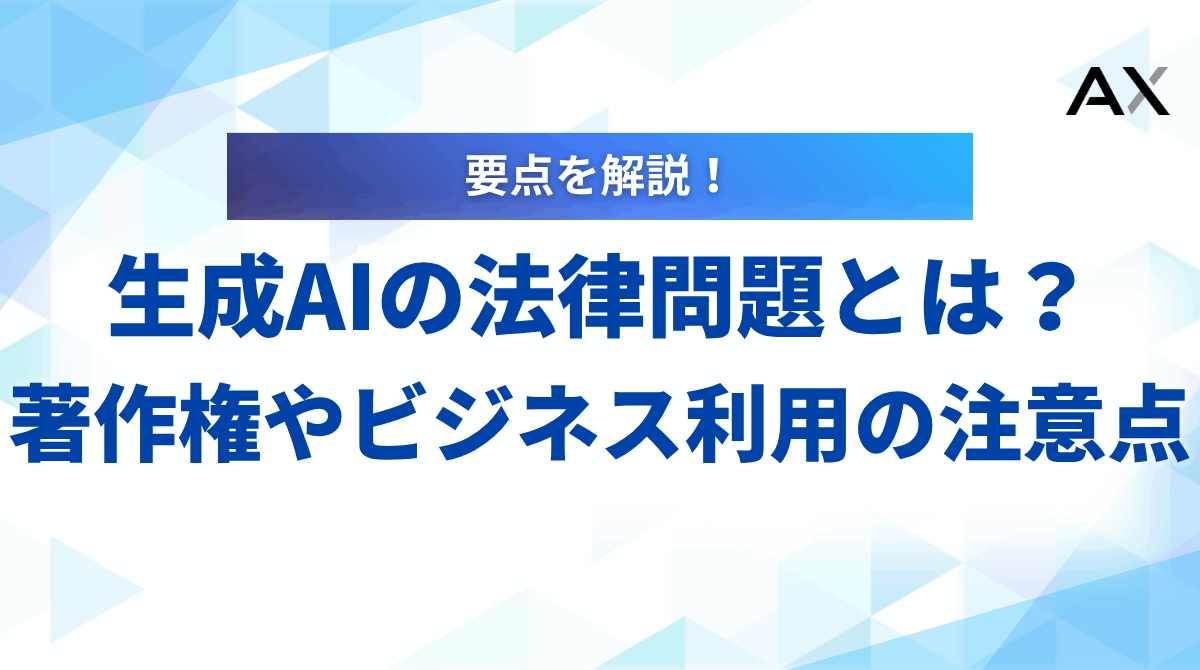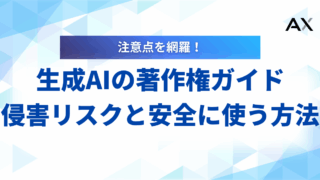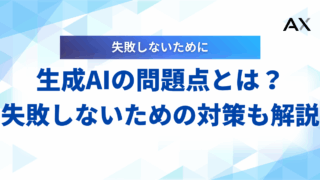生成AIをビジネスに導入したいけれど、著作権侵害や情報漏洩のリスクが怖い。自社で安全に活用するためには、どんな法律に注意すれば良いのか分からない。このような悩みを抱える法務・事業開発担当者の方は多いのではないでしょうか。
生成AIの技術は日々進化しており、法整備もそれに追いつこうと国内外で急速に進んでいます。気づかないうちに法律違反をしていた、という事態は絶対に避けなければなりません。
この記事では、2026年時点の最新情報に基づき、生成AIに関わる著作権法や個人情報保護法などの法律問題を分かりやすく解説します。さらに、今後施行が見込まれる日本の「AI新法」や海外の規制動向、そしてビジネスで実践できる具体的なリスク対策までを網羅的にご紹介。最後までお読みいただくことで、法的な不安を解消し、自信を持って生成AI活用を推進するための知識が身につきます。
AX CAMPでは、こうしたリスクへの対応も含めた、実践的なAI活用研修をご提供しています。専門家が監修した最新のガイドラインをまとめた資料もご用意しておりますので、ぜひこの機会にご覧ください。
記事:【AI導入しないことが経営リスクになる時代】先行企業が手にした圧倒的な競争優位とは?
生成AIと法律の基本関係

生成AIと法律の関係を理解する上で最も重要なのは、AIが単独で生成したものには、原則として著作権が発生しにくいという点です。日本の著作権法は、人間の「思想又は感情を創作的に表現したもの」を「著作物」として保護します。AIが自律的に生成したものはこの定義に当てはまらないと解釈されるのが一般的ですが、これは全てのケースに当てはまるわけではありません。
重要なのは、人間がAIを「道具」として用い、その過程に創造的な貢献(創作的寄与)が認められる場合です。この場合、生成物は人間の著作物として保護される可能性があります。しかし、具体的な利用前には個別の事案や利用規約、さらには海外の法律も考慮する必要があり、状況の確認と記録が不可欠です。この「創作的寄与」の有無が、生成AI時代の権利関係を読み解く鍵となります。
AI生成物は「著作物」として認められるか
文化庁の見解によれば、AI生成物であっても、人間が「創作意図」を持ち、AIへの具体的な指示などを通じて「創作的寄与」が認められれば、その人が著作者になり得ます。 例えば、単に「猫の絵を描いて」と指示するだけでは不十分ですが、構図や色彩、画風、表情などを細かく指示し、生成と修正を繰り返して完成させた場合、その一連の行為に創作性が認められ、著作物となる可能性が高まります。
現状、どこからが「創作的寄与」と認められるかの明確な線引きは確立されていません。今後の判例蓄積が待たれますが、ビジネス利用においては、AIへの指示内容(プロンプト)や編集・加工の履歴を記録しておくことが、将来的な権利主張の際に重要な証拠となります。
AIと人間の共同制作における権利の所在
AIと人間が共同でコンテンツを制作した場合、その権利は創作的寄与を行った人間に帰属するのが基本です。AIは法律上の権利主体とはなれないため、あくまで高度な道具という位置づけになります。したがって、生成物の著作権を主張するには、人間がいかに創作へ関与したかを具体的に示す必要があります。
ただし、利用する生成AIサービスの利用規約には注意が必要です。サービスによって、生成物の権利をユーザーに譲渡する場合もあれば、提供者が保持したり、商用利用に制限を設けたりするケースもあります。自社の権利を確保するためには、サービス選定時に利用規約を精査することが不可欠です。特に、入力データがAIの再学習に利用されないか(オプトアウト可能か)という点は、情報漏洩リスクの観点から必ず確認しましょう。
生成AIの学習・開発段階で注意すべき法律

生成AIの開発・学習段階では、日本の著作権法が技術革新を後押しする側面があります。著作権法第30条の4では、AI開発のような「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(非享受目的)」の場合、一定の条件下で著作権者の許諾なく既存の著作物を利用できると定められています。
しかし、この規定は万能ではありません。「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は例外とされており、その解釈が重要な論点となります。 契約上の制約や、学習データの二次利用・モデル公開時の影響も踏まえ、個別の法的検討とリスク評価が不可欠です。(出典:AIと著作権に関する考え方について | 文化庁) また、学習データに個人情報が含まれる場合は、個人情報保護法への配慮が必須です。
著作権法30条の4(非享受目的の利用)の解釈
著作権法30条の4は、AI開発でコンピュータが大量の情報を解析するケースなどを想定した条文です。 この規定により、日本のAI開発者は、個々の著作権者に許諾を得ることなく、インターネット上の膨大なデータを学習させることが原則として可能になっています。
しかし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、この条文の適用が除外されます。 例えば、学習用に作られたデータベースを販売するなど、本来著作権者が利益を得るはずの市場と競合する利用方法や、海賊版サイトから違法に収集した著作物を学習データに使うケースは、これに該当する可能性が指摘されています。
どのケースが「不当に害する」にあたるかは、まだ判例が少なく議論が続いていますが、企業がAIを開発・利用する際には、この例外規定の存在を常に念頭に置く必要があります。
(出典:AIと著作権に関する考え方について)
個人情報保護法とプライバシー権への配慮
生成AIの学習データに個人情報(氏名、住所、顔写真など)が含まれる場合、著作権法だけでなく個人情報保護法が適用されます。学習目的であっても、個人情報を取得・利用する際には、利用目的を本人に通知または公表する義務があります。また、データが漏洩しないよう、適切な安全管理措置を講じることも求められます。
特に、顧客情報や従業員情報を学習データとして利用する際には細心の注意が必要です。万が一、学習させた個人情報が生成物として外部に出力されれば、重大なプライバシー侵害につながります。原則として個人情報の学習データ化は避けるべきですが、業務上必要な場合は、本人の同意取得や法的根拠の確認、そして匿名化・仮名加工、アクセス制御といった安全管理措置を徹底する必要があります。
生成AIの利用・生成段階で注意すべき法律

生成AIを利用してコンテンツを作成する段階では、法律上のリスクが大きく変わります。学習段階とは異なり、生成物が既存の著作物と類似している場合、意図せずとも著作権侵害になる可能性があります。 著作権侵害が認められた場合の責任は、契約内容、過失の有無、提供者の注意義務など様々な要因に依存しますが、生成物を利用したユーザーが責任を問われる可能性は十分にあります。
そのため、生成されたコンテンツを公開したり商用利用したりする前には、慎重な確認が求められます。また、人物の画像を生成する際には、著作権だけでなく、その人物の肖像権やパブリシティ権を侵害しないよう配慮することも重要です。
生成物が既存の著作物と類似した場合の著作権侵害リスク
AIによる生成物が著作権侵害と判断されるには、主に2つの要件を満たす必要があります。一つは、既存の著作物と表現が似ていること(類似性)、もう一つは、既存の著作物をもとに創作されたこと(依拠性)です。
ここでAI特有の問題となるのが「依拠性」の判断です。利用者が元の著作物を全く知らなくても、AIがその著作物を学習していれば、「依拠性あり」と判断されるリスクがあります。 偶然の一致だと証明することは極めて困難なため、特に作風に特徴のあるクリエイターの作品や、特定のキャラクターに酷似した生成物を利用する際は、高いリスクを伴います。ビジネス利用では、生成物のオリジナリティをツールでチェックしたり、特定のアーティスト名をプロンプトに含めないといった対策が有効です。
肖像権・パブリシティ権の侵害リスク
実在の人物、特に有名人の写真や名前を使って画像を生成すると、肖像権やパブリシティ権の侵害となるおそれがあります。肖像権は、みだりに自らの容姿を撮影・公表されない権利であり、パブリシティ権は、有名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を無断で利用されない権利です。
例えば、特定の俳優に似せた画像を生成し、それを広告に利用した場合、パブリシティ権の侵害を問われる可能性が高いでしょう。また、一般人の写真であっても、本人の許可なくAIアバターを作成してSNSで公開するような行為は、肖像権侵害にあたる可能性があります。ディープフェイク技術の悪用が社会問題化していることもあり、人物画像の生成・利用には倫理的な配慮が強く求められます。
【2026年施行】AI新法の概要とビジネスへの影響

2025年、日本ではAIに特化した初の横断的な法律である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(通称:AI推進法)が公布・施行されました。 この法律は、イノベーションの促進を主眼としており、罰則を伴う厳しい規制(ハードロー)ではなく、事業者の自主的な取り組みを促す「推進法」としての性格を持っています。
この法律は2025年5月28日に成立され、同年6月4日に公布し同日に一時施行。2025年9月1日に全面施行されました。 法律の施行により、企業にはAI開発・活用プロセスの透明性確保や、リスク発生時の説明責任がより一層求められるようになります。特に、医療やインフラといった国民の権利利益に大きな影響を与える分野では、将来的に規制が強化される可能性も視野に入れておく必要があります。(出典:人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の閣議決定について – 内閣府)
AI推進法では、内閣総理大臣を本部長とする「AI戦略本部」が設置され、国全体のAI政策をまとめた「AI基本計画(人工知能基本計画)」を策定します。 事業者は、政府の調査や指導への協力義務を負うことになります。 この法律は、AIを安全に利活用するための社会的な基盤を整備するものであり、企業は自社のAIガバナンス体制を構築・強化することが急務となるでしょう。(出典:AI戦略 – 科学技術・イノベーション – 内閣府)
生成AIの法律トラブルを避けるための実践的対策

生成AIをめぐる法律トラブルを未然に防ぐためには、技術的な理解だけでなく、組織的なルール作りが不可欠です。具体的には、「利用するAIサービスの規約を徹底的に確認すること」と、「自社の状況に合わせた社内利用ガイドラインを策定すること」の2点が最も重要な実践的対策となります。これらを整備することで、従業員が安心してAIを活用できる環境を整え、法的リスクを組織的に管理することが可能になります。
ルールを定めるだけでなく、従業員一人ひとりのリテラシーを向上させるための継続的な教育も欠かせません。法律やツールの仕様は日々変化するため、定期的に最新情報を共有し、意識を高める取り組みが求められます。
利用規約の確認と商用利用の可否判断
生成AIサービスを選定する際、機能や料金だけでなく利用規約の確認が極めて重要です。特に以下の点は必ずチェックしましょう。
- 生成物の権利帰属:生成したコンテンツの著作権はユーザーに帰属するのか、それともサービス提供者が保持するのか。
- 商用利用の可否:生成物を自社の製品や広告、マーケティング資料などに利用できるか。範囲に制限はないか。
- 入力情報の取り扱い:入力したプロンプトやデータが、AIの再学習に利用されるか。オプトアウト(学習への利用を拒否する設定)が可能か。
- 学習データの透明性:どのようなデータセットで学習したAIモデルか。権利的にクリーンなデータを使用しているか公表されているか。
これらの項目を確認せずに利用を開始すると、意図せず規約違反を犯したり、機密情報がAIの学習データとして流出したりするリスクがあります。法務部門と連携し、リスク評価を行った上で導入を判断するプロセスを確立しましょう。
社内向け「生成AI利用ガイドライン」の策定ポイント
従業員が安全かつ効果的に生成AIを利用するためには、明確な社内ガイドラインが必須です。ゼロから作成するのは大変ですが、日本ディープラーニング協会(JDLA)などが公開している雛形を参考に、自社向けにカスタマイズするのが効率的です。
ガイドラインに盛り込むべき主要なポイントは以下の通りです。
- 基本方針と目的:AI活用による生産性向上といったポジティブな目的を明記する。
- 利用申請と承認プロセス:どのツールを、どの部署が、どのような目的で利用するのかを明確にするフローを定める。
- 入力禁止情報の定義:個人情報、顧客情報、非公開の技術情報など、入力してはならない情報を具体的にリストアップする。
- 生成物の利用ルール:著作権等の権利確認手順、ファクトチェックの義務、社外公開時の承認プロセスなどを定める。
- セキュリティと倫理:パスワード管理の徹底や、差別・偏見を助長するような利用の禁止を明記する。
- トラブル発生時の報告体制:問題を発見した場合の報告先と対応フローを定めておく。
これらのガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することで、組織全体のリスク耐性を高めることができます。
海外における生成AIの法規制動向

生成AIの法規制は世界的な課題であり、主要国がそれぞれ独自のアプローチでルール整備を進めています。特にEUが包括的な規制法「AI Act」で先行し、米国や中国がそれに続く形となっています。グローバルに事業を展開する企業にとって、これらの国々の規制動向を把握し、準拠していくことは不可欠です。各国の規制は、データガバナンスや製品開発のあり方に直接影響を与えるため、継続的な情報収集が求められます。
各国のアプローチには違いがあり、EUは人権保護を重視したリスクベースの規制、米国はイノベーション促進とのバランスを重視、中国は国家による統制を強める傾向が見られます。
EU:包括的規制「AI Act」が先行
EUでは、世界に先駆けて包括的なAI規制法である「AI Act(AI法)」が2024年5月に成立し、段階的に適用が開始されています。 この法律の最大の特徴は、AIシステムがもたらすリスクを4段階(「許容できないリスク」「高リスク」「限定的リスク」「最小リスク」)に分類し、リスクのレベルに応じて異なる義務を課す「リスクベース・アプローチ」を採用している点です。
例えば、サブリミナル操作や社会的スコアリングなど「許容できないリスク」を持つAIは原則禁止されます。 一方、インフラ、医療、採用などで使われる「高リスクAI」の提供者には、データガバナンス、技術文書の作成、透明性の確保、人間の監視など、厳格な義務が課せられます。 違反した場合には巨額の制裁金が科される可能性があり、EU市場で事業を行う日本企業も対応が必須となります。(出典:EU理事会、AI法案を採択、2026年中に全面適用開始へ(EU) | ビジネス短信 – ジェトロ)
米国:イノベーションと規制のバランスを重視
米国では、EUのような単一の包括的な法律ではなく、既存の分野別規制の活用や、大統領令を通じたガイドライン策定など、柔軟なアプローチが取られています。AIによるイノベーションを阻害しないことを重視しつつ、安全性や公正性、プライバシー保護といった課題に対応する姿勢です。
2025年1月の政権交代以降、AI開発を促進し規制障壁を排除する方向性が示されています。しかし、連邦レベルでの政策とは別に、カリフォルニア州やコロラド州など、各州で独自のAI規制法案の審議が進んでおり、企業は連邦と州、双方の動向を注視する必要があります。米国国立標準技術研究所(NIST)が公表した「AIリスク管理フレームワーク(AI RMF)」は、法的な拘束力はないものの、多くの企業がリスク管理の指針として参照しています。
中国:国家管理下での利用を推進
中国におけるAI規制は、国家の安全保障と社会の安定を重視し、政府による強い統制が特徴です。2023年8月15日に施行された「生成AIサービス管理暫定弁法」では、生成AIサービスを提供する事業者に対して、当局への安全性評価の申請やアルゴリズムの登録を義務付けています。
また、生成されるコンテンツは社会主義の基本的価値観に沿うものであることを求めており、国家転覆を扇動するようなコンテンツの生成は固く禁じられています。中国で事業を展開する企業は、これらの規制を遵守することはもちろん、データ越境移転に関する厳しい規制にも対応する必要があります。テクノロジーの発展を国家戦略として強力に推進する一方で、その利用方法を厳しく管理するというのが中国のアプローチです。(出典:生成式人工智能服务管理暂行办法)
法務リスクを抑えたAI活用ならAX CAMPの研修がおすすめ

ここまで解説してきたように、生成AIのビジネス活用には、著作権法、個人情報保護法、そして国内外の新たなAI規制など、多岐にわたる法務リスクへの対応が不可欠です。最新の法改正や各国の規制動向を常に把握し、自社の利用状況に合わせてガイドラインを更新し続けるのは、法務部門や事業推進担当者にとって大きな負担となり得ます。
「AIの専門家の知見を借りながら、効率的にリスク管理体制を構築したい」「従業員のリテラシーを底上げし、全社で安全なAI活用を推進したい」とお考えなら、AX CAMPの実践型AI研修がその課題解決をサポートします。
AX CAMPの法人向け研修プログラムでは、単なるツールの使い方を学ぶだけではありません。本記事で解説したような法務・倫理的リスクに関する最新の知識や、安全な利用を実現するための社内ガイドライン策定のノウハウについても、専門家の監修のもとで体系的に学ぶことができます。研修を通じて、各部門の担当者が自社の業務に潜むリスクを自ら発見し、対策を立案できるスキルを養うことを目指します。
自社のAI活用レベルや、現在抱えている課題について、まずは意見を聞いてみたいという方は、ぜひ一度、無料相談会にお申し込みください。貴社の状況に最適な研修プランをご提案します。
まとめ:生成AIの法律を理解し安全なビジネス活用を
本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、生成AIの活用に伴う法律問題と、企業が取るべき実践的な対策について解説しました。急速に進化する技術と法規制の動向を正しく理解し、リスクを管理することが、安全で持続可能なAI活用の鍵となります。
最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- AI単独の生成物は著作物になりにくい:原則としてAI単独の生成物に著作権は発生しにくいですが、人間の「創作的寄与」が認められれば著作物として保護される可能性があります。
- 学習段階と利用段階のリスクは異なる:AIの学習は著作権法30条の4で条件付きで認められるが、生成物が既存の著作物と類似すると著作権侵害のリスクがある。
- 個人情報・機密情報の入力は原則禁止:情報漏洩やプライバシー侵害を防ぐため、ガイドラインで明確に禁止し、例外的な利用には厳格な安全措置を講じる必要がある。
- 国内外で法整備が進行中:日本の「AI推進法」やEUの「AI Act」など、最新の規制動向を常に把握し、対応することが不可欠。
- 実践的な対策が重要:利用規約の確認と、自社の実態に合わせた社内ガイドラインの策定・運用がリスク回避の要となる。
これらの法的要件を遵守し、社内体制を整備することは、時に複雑で困難な作業に感じられるかもしれません。しかし、適切なリスク管理は、企業を守るだけでなく、従業員が安心して新しい技術を活用し、イノベーションを創出するための土台となります。
AX CAMPでは、専門的な知見に基づき、貴社のAI活用における法務・セキュリティ体制の構築を支援します。最新の研修プログラムや、ガイドライン策定の伴走支援を通じて、貴社が直面する課題を解決に導きます。生成AIの導入や活用に関するお悩みは、ぜひお気軽にAX CAMPの無料相談でご相談ください。