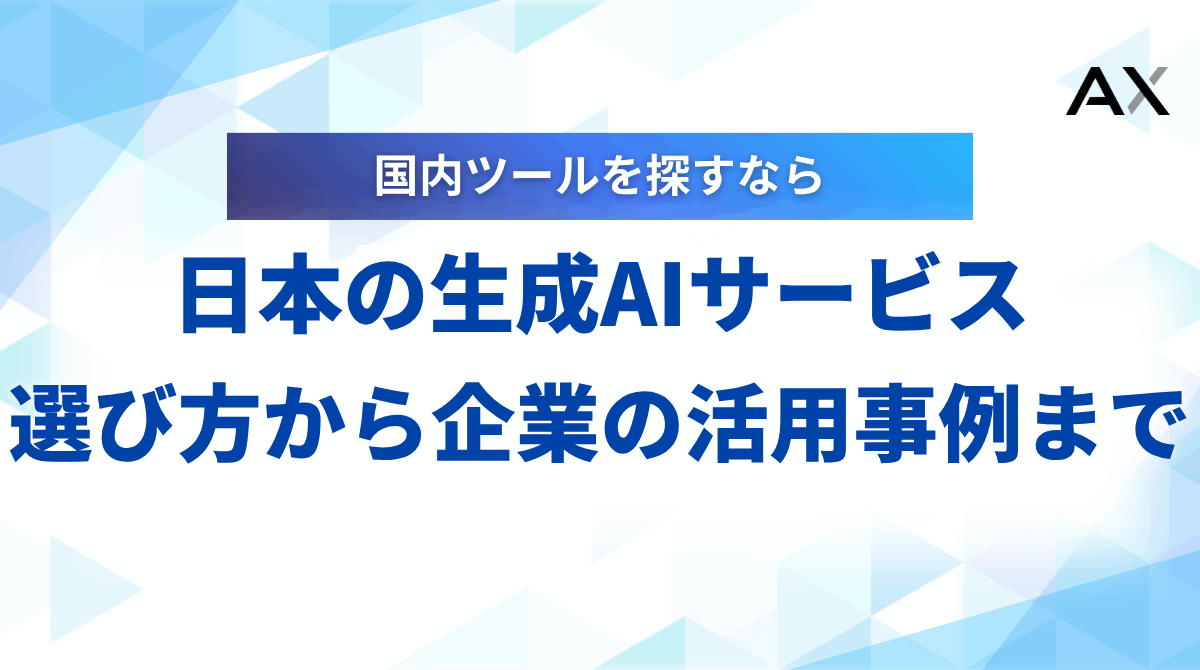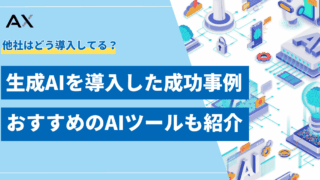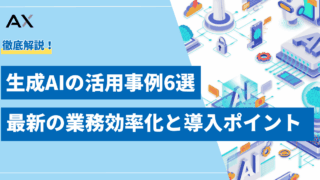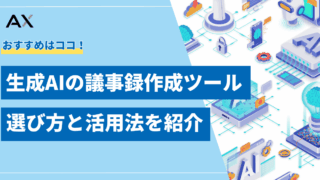「日本で使える生成AIにはどんなものがある?」
「自社に最適なサービスをどう選べばいいのかわからない」――。
そんな悩みを抱える企業担当者の方も多いのではないでしょうか。2025年現在、日本国内でもビジネス活用を目的とした多様な生成AIサービスが登場し、業務効率化や新たな価値創造の切り札として注目されています。この記事では、最新の日本製大規模言語モデルから、具体的な業務効率化ツール、そして自社に最適なサービスを選ぶための3つのポイントまで、網羅的に解説します。
成功事例も交えながら、あなたの会社が生成AI導入で成果を出すための具体的なヒントを提供します。AI導入の全体像を掴みたい方は、AX CAMPが提供するお役立ち資料もぜひご活用ください。
2025年注目の日本製・日本語対応の大規模言語モデル(LLM)3選

2025年、日本のビジネス環境に特化した高性能な大規模言語モデル(LLM)が次々と登場し、注目を集めています。これらのモデルは、海外製LLMと比較して日本語の複雑なニュアンスや文化的背景への理解が深く、国内企業の多様なニーズに応える高いポテンシャルを秘めています。特に、NTT、NEC、ELYZAの3社が開発するLLMは、それぞれ独自のアプローチで高い性能を実現しており、今後のビジネス活用において重要な選択肢となるでしょう。
これらの日本製LLMは、単に日本語性能が高いだけでなく、提供形態や契約によっては国内の法規制やデータ保護要件に適合させやすい利点があります。企業の機密情報を扱う業務でも安心して利用できる選択肢が整いつつあるのです。ここでは、それぞれのLLMが持つ特長と、ビジネスにおける活用可能性について詳しく見ていきましょう。
1. tsuzumi (NTT)
NTTが開発した「tsuzumi」は、軽量でありながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つとされる大規模言語モデルです。パラメータサイズを6億から70億と、他の大規模モデルと比較して意図的に小さく抑えることで、計算資源の要件を下げ、導入・運用コストの大幅な低減を実現しています。(出典:NTT版大規模言語モデル「tsuzumi」) これにより、従来はコスト面で導入が難しかった企業でも、自社専用の環境でAIをカスタマイズして活用する道が開かれました。
さらに、特定の業界や企業の専門用語に合わせて柔軟にチューニングできる「アダプタ形式」を採用しており、金融や医療、自治体など、専門性が求められる分野での活躍が期待されています。2024年3月に商用サービスが開始され、将来的には画像なども理解するマルチモーダルへの対応も進められています。
2. cotomi (NEC)
NECが提供する生成AI「cotomi(コトミ)」は、グローバルトップレベルの性能を高速で実現することを目指した日本語に強いLLMです。高性能なモデルと、より高速処理が可能な軽量モデルのラインナップがあり、用途に応じて選択できます。これにより、企業の多様なニーズへ柔軟な対応が可能です。(出典:NEC、生成AI「cotomi(コトミ)」の強化・拡充と共に生成AI事業戦略を発表)
ビジネスにおいては、社内文書の検索システムやコールセンターの応答支援など、速度と正確性が求められる場面でその真価を発揮します。実際にNECグループ社員約4万人が約1年間利用し、そのフィードバックを基に性能を向上させており、実用性の高さが証明されているモデルと言えるでしょう。
3. ELYZA LLM for JP (ELYZA)
株式会社ELYZAが開発した「ELYZA LLM for JP」は、日本語の読解力と指示理解能力において、優れた性能を持つLLMです。Meta社の高性能モデル「Llama 3」系列をベースに、ELYZAが独自に日本語の追加学習を施すことで、高い日本語性能を実現しました。社内ベンチマーク評価では、モデルによって「GPT-5」を上回る性能を達成したと報告されています。
金融業界をはじめとする大企業での導入実績もあり、その安全性と信頼性は高く評価されています。(出典:ELYZA、日本語性能でGPT-5を上回る70億パラメータのLLM「ELYZA-japanese-Llama-2-7b」を一般公開) 複雑な契約書や報告書の要約、精度の高い文章作成、高度な質疑応答など、専門的かつ正確性が求められる業務での活用に適しています。国内の法規制やデータ保護にも対応しやすく、企業のニーズに応じた柔軟な活用が可能です。
【業務効率化】日本企業向け生成AIサービス3選

生成AIを実際の業務で活用し、効率化を実現するためには、セキュリティと管理機能が充実した法人向けサービスを選ぶことが不可欠です。個人向けサービスとは異なり、法人向けツールは情報漏洩リスクへの対策やユーザーごとの権限管理、利用状況のモニタリング機能などを備えており、企業が安心して導入できる設計になっています。
現在、日本市場では多様な法人向け生成AIサービスが提供されていますが、ここでは特に多くの企業で導入実績があり、業務効率化に直結する機能を備えた3つの代表的なサービスを紹介します。これらのサービスは、いずれも複数の高性能LLMを選択できたり、業務に特化したテンプレートを備えていたりと、実用性の高い工夫が凝らされています。
1. 法人GAI (株式会社ギブリー)
株式会社ギブリーが提供する「法人GAI」は、企業のセキュリティ要件に対応したセキュアな環境でChatGPTなどの生成AIを利用できるプラットフォームです。入力したデータがAIの学習に利用されることを防ぐ機能や、IPアドレスによるアクセス制限など、法人利用で不可欠なセキュリティ機能を標準搭載しています。(出典:ギブリー、生成AI・AIエージェント活用プラットフォーム「MANA Studio」にて「GPT-5」に対応開始)
また、GPT-5など複数の高性能LLMの中から業務内容に応じて最適なモデルを選択できる点も大きな特長です。 部署や役職に応じた利用権限の設定も可能で、全社的なガバナンスを効かせながら生成AIの活用を推進したい企業に適しています。
2. exaBase 生成AI (株式会社エクサウィザーズ)
株式会社エクサウィザーズが提供する「exaBase 生成AI」は、2023年の提供開始からわずか2年で利用ユーザー数が10万人を突破した、市場シェアNo.1の法人向け生成AIサービスです。高いセキュリティと、業務ですぐに使える150種類以上の「プロンプトテンプレート」が強みで、多くの企業で生産性向上に貢献しています。(出典:エクサウィザーズの法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」、利用ユーザー数が10万人を突破)
導入企業では、ひと月あたり2,500人分の業務時間削減を達成したという実績もあります。資料作成やデータ分析といった複雑な作業をAIエージェントが自動化する機能も備えており、専門知識がない従業員でも簡単にAIの恩恵を受けられるよう設計されています。
3. SPESILL (株式会社ファースト・オートメーション)
株式会社ファースト・オートメーションが提供する「SPESILL(スペシル)」は、特に製造業のデスクワークを効率化することに特化した生成AIツールです。仕様書や報告書、手順書といった専門文書の自動生成に強みを持ち、ExcelやWordに直接反映させることで、技術者の作業負担を大幅に軽減します。(出典:ELYZA、Llama 3.1ベースの日本語モデルを開発)
フローチャートやレイアウト図の自動生成機能も搭載しており、これまで専門ソフトで時間のかかっていた作図業務も効率化できます。専門性が高く、定型的な文書作成が多い技術部門や開発部門を抱える企業にとって、即戦力となるサービスです。
【用途別】特定業務に特化した日本の生成AIツール2選

汎用的な対話型AIだけでなく、特定の業務領域に特化して設計された生成AIツールは、導入後すぐに高い費用対効果を発揮しやすいというメリットがあります。これらのツールは、特定の業務フローに最適化された機能を持っているため、現場の担当者が特別な知識なしで直感的に利用でき、短期間で成果に繋げることが可能です。ここでは、多くの企業で共通の課題となっている「議事録作成」と「社内ナレッジ検索」の2つの用途に絞り、代表的な日本の生成AIツールを紹介します。
議事録作成・文字起こし
会議の議事録作成は、多くの時間を要する定型業務の代表格です。この課題を解決するのが、AIによる文字起こし・議事録作成ツールです。例えば、「Rimo Voice」といったサービスは、会議中の音声をリアルタイムでテキスト化し、話者分離や要約、さらには決定事項の抽出まで自動で行います。
これにより、担当者は煩雑な文字起こし作業から解放され、会議の内容把握と次のアクションに集中できます。また、会議に参加できなかったメンバーへの情報共有も迅速かつ正確に行えるようになり、組織全体の生産性向上に大きく貢献します。日本語の高い認識精度を持つツールが多く、専門用語にも対応できるため、様々な業種の会議で活用されています。
社内ナレッジ検索・FAQシステム
「あの資料はどこにあったか」「この業務の担当者は誰か」といった社内での情報探しに費やす時間は、見えないコストとして業務を圧迫します。この問題を解決するのが、社内文書やマニュアルを学習させたAIが質問に自動で回答するナレッジ検索・FAQシステムです。代表的なサービスとして「ナレカンAI」や、多くの法人向け生成AIプラットフォームが提供するRAG(検索拡張生成)機能が挙げられます。
これらのシステムは、社内に散在する膨大な情報の中から、AIが最適な回答を瞬時に探し出して提示します。これまで担当部署に問い合わせないと分からなかった情報も、従業員が自己解決できるようになるため、問い合わせ対応部署の負担軽減と、従業員全体の業務効率化を同時に実現します。
日本で生成AIを導入する主なメリット2つ

日本企業が生成AIを導入することで得られる最大のメリットは、「定型業務の自動化による生産性向上」と「データ分析に基づく迅速な意思決定」の2点に集約されます。これらは、人手不足や変化の激しい市場環境といった、現代の日本企業が直面する大きな課題に対する強力な解決策となり得ます。生成AIは単なる業務効率化ツールに留まらず、企業の競争力そのものを高める戦略的な一手となるのです。
定型業務の自動化による生産性向上
生成AIは、これまで人間が時間をかけて行っていた定型業務を自動化し、従業員をより付加価値の高い創造的な業務へシフトさせることを可能にします。例えば、メールの文面作成、会議の議事録要約、各種レポートの草案作成、データ入力といった日常的なタスクをAIに任せることで、従業員一人ひとりの業務時間を大幅に削減できます。
実際に、ソフトバンクでは生成AIの活用により、ある病院業務において年間6,000時間分の生産性向上を実現した事例もあります。(出典:ソフトバンク株式会社 法人向け導入事例) このように創出された時間を、企画立案や顧客との対話、新たなスキル習得といった、人間にしかできない業務に充てることで、企業全体の生産性を飛躍的に向上させることができるのです。
データ分析に基づく迅速な意思決定
現代のビジネス環境では、膨大なデータの中からいかに早く的確なインサイトを抽出し、経営判断に活かすかが成功の鍵を握ります。生成AIは、その卓越したデータ処理能力によって、市場トレンドの分析、顧客データの要約、競合の動向調査などを瞬時に行い、意思決定者に客観的な判断材料を提供します。
例えば、日々の売上データや顧客からのフィードバック、SNS上の口コミといった大量のテキストデータをAIに分析させることで、これまで気づかなかった新たなビジネスチャンスや潜在的なリスクを早期に発見できます。これにより、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定が可能となり、変化の激しい市場での競争優位性を確立することに繋がります。
日本企業が生成AIサービスを選ぶ際の3つのポイント

自社に最適な生成AIサービスを導入し、失敗を避けるためには、「利用目的の明確化」「日本語処理能力とセキュリティの確認」「コストとサポート体制の評価」という3つのポイントを総合的に検討することが極めて重要です。これらの基準を持たずに流行だけでツールを選んでしまうと、「導入したものの使われない」「期待した効果が出ない」といった事態に陥りかねません。事前にこれらのポイントをしっかりと吟味することで、投資対効果を最大化し、生成AIの導入を成功に導くことができます。
1. 利用目的と機能の適合性
まず、「何のために生成AIを導入するのか」という目的を明確にする必要があります。例えば、「マーケティング部門の広告コピー作成を効率化したい」「カスタマーサポートの問い合わせ対応を自動化したい」「全社的な情報検索の時間を短縮したい」など、具体的な業務課題を洗い出します。
目的が明確になれば、それに必要な機能が見えてきます。文章生成、要約、翻訳、画像生成、データ分析など、サービスによって得意な機能は異なります。解決したい課題とツールの機能が合致しているかを丁寧に見極めることが、導入成功の第一歩です。
2. 日本語処理能力とセキュリティ
日本のビジネスで利用する以上、日本語の処理能力は非常に重要な選定基準です。特に、業界特有の専門用語や日本語ならではの曖昧な表現、敬語などをどれだけ正確に理解し、自然な文章を生成できるかを確認する必要があります。多くのサービスで無料トライアルが提供されているため、実際の業務に近い内容でテストし、日本語の精度を評価しましょう。
同時に、法人利用で最も重視すべきなのがセキュリティです。入力した機密情報や個人情報がAIの学習データとして二次利用されないか、通信が暗号化されているか、アクセス管理機能は十分かなど、自社のセキュリティポリシーを満たしているかを厳しくチェックすることが不可欠です。
3. コストとサポート体制
生成AIサービスの料金体系は、月額固定制、利用量に応じた従量課金制、ユーザー数に基づくライセンス制など様々です。自社の利用頻度やユーザー数を想定し、どの料金プランが最もコストパフォーマンスに優れているかをシミュレーションしましょう。無料プランやトライアル期間を活用して、機能とコストのバランスを見極めることも重要です。
また、導入後の運用をスムーズに進めるためには、提供元のサポート体制も確認すべきポイントです。導入時のトレーニングや、利用中の技術的な問い合わせに対応してくれる窓口があるか、日本語でのサポートが受けられるかなど、万が一の際に頼れる体制が整っているサービスを選ぶと安心です。
日本企業における生成AIの導入成功事例2選

業種や企業規模を問わず、多くの日本企業が生成AIを導入し、具体的な業務改善や新たな価値創出といった成果を上げています。ここでは、AX CAMPの支援を通じて、特に顕著な成果を達成した2社の事例を紹介します。これらの事例から、生成AIがどのように現場の課題を解決し、ビジネスの成長に貢献するのか、具体的なイメージを掴んでいただけるはずです。
株式会社Inmark:広告チェック業務を2週間で完全自動化
Web広告運用代行を手掛けるInmark様は、毎日の広告チェック業務に多くの時間を費やしているという課題を抱えていました。この定型的ながらも重要な業務を効率化するため、AX CAMPでAIツールの活用方法を学び、業務の自動化に着手しました。
その結果、AX CAMPでの学習開始からわずか2週間で、これまで毎日1時間以上かかっていた広告チェック業務のほぼ完全な自動化に成功しました。創出された時間は、より戦略的な広告プランの策定や顧客への提案といった、付加価値の高い業務に充てられています。(出典: AX CAMP受講企業の成果事例)
WISDOM合同会社:AI活用で採用2名分の作業量を代替
SNS広告やショート動画制作を行うWISDOM合同会社様は、事業拡大に伴う人材採用コストと業務負荷の増大に直面していました。この課題に対し、AX CAMPの研修を通じて習得したAIスキルを活用し、徹底的な業務自動化を推進しました。
その結果、採用2名分に相当する作業量をAIで代替することに成功し、採用コストを抑制しながら事業を成長させる体制を構築しました。AIを単なる効率化ツールとしてではなく、経営資源の一部として戦略的に活用した好例です。(出典: AX CAMP受講企業の成果事例)
日本の生成AIに関するよくある質問

日本国内で生成AIの導入を検討する際には、技術的な側面だけでなく、法規制や導入対象となる企業の規模など、様々な疑問が生じます。ここでは、特に多くの企業担当者から寄せられる質問について、簡潔に解説します。これらのFAQを通じて、導入に向けた不安や疑問を解消し、より具体的な検討ステップに進むための一助としてください。
日本で生成AIを導入する際の法的な注意点はありますか?
はい、特に「著作権法」と「個人情報保護法」には注意が必要です。生成AIが作成したコンテンツが、既存の著作物と類似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」などの資料を参考に、生成物の利用範囲について理解を深めることが重要です。
また、顧客情報や従業員情報などの個人情報をプロンプトとして入力すると、個人情報保護法に抵触する可能性があります。対策として、社内ガイドラインを策定し、個人情報や機密情報の入力を原則禁止する、データが二次学習に利用されない法人向けサービスを選定するなど、情報の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。最終的な法務判断については、弁護士などの専門家にご相談ください。
中小企業でも生成AIを導入することは可能ですか?
はい、十分に可能です。かつてAI導入には多額の設備投資や専門人材が必要でしたが、現在では月額数千円から利用できるクラウド型の生成AIサービスが多数登場しており、中小企業でも導入のハードルは劇的に下がっています。
東京商工会議所が2024年5月に実施した調査では、生成AIを「活用している」中小企業は11.7%、「今後活用を検討している」企業は33.5%にのぼり、関心の高さがうかがえます。 人材不足や資金不足といった中小企業特有の課題を解決する強力なツールとして、生成AIへの期待は高まっています。(出典:中小企業のための 「生成AI」活用入門ガイド – 東京商工会議所)
専門家による伴走支援ならAX CAMPのAI研修

「自社に最適なAIツールがわからない」「導入しても現場で使いこなせるか不安だ」といった課題を抱えていませんか。生成AIの導入で本当に成果を出すためには、ツールの導入だけでなく、自社の業務に合わせた具体的な活用方法を学び、全社的に実践していく体制が不可欠です。
私たちAX CAMPが提供する法人向けAI研修は、単なるツールの使い方を教えるだけではありません。貴社のビジネス課題をヒアリングし、どの業務にAIを適用すれば最も効果的か、という戦略立案から伴走します。実務に直結するカリキュラムを通じて、受講者が自ら業務を自動化・効率化できるスキルを習得することを目指します。
ご契約プランに応じて、研修後も専門家による継続的なサポートを提供しており、新たなAI技術のアップデートにも迅速に対応できる体制を整えています。「AIを導入して終わり」ではなく、「AIを使いこなし成果を出し続ける」組織への変革を、AX CAMPが強力に支援します。まずは無料相談で、貴社の課題をお聞かせください。
まとめ:生成AIを日本で活用しビジネスを加速させよう
本記事では、2026年時点における日本国内の生成AIサービスと、その選び方、活用事例について解説しました。改めて、重要なポイントを以下にまとめます。
- 日本のLLMも進化:NTTの「tsuzumi」やNECの「cotomi」など、日本語に強く、国内のビジネス環境に適した高性能な大規模言語モデルが登場している。
- 法人向けサービスが鍵:業務で活用する際は、セキュリティや管理機能が充実した法人向けサービスを選ぶことが不可欠。
- 選び方の3つの軸:「目的の明確化」「日本語能力とセキュリティ」「コストとサポート」を基準に、自社に最適なツールを選定することが成功の分かれ道。
- 中小企業こそ活用を:クラウドサービスの普及により、低コストで導入が可能になり、人手不足などの課題解決に直結する。
生成AIは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。定型業務を自動化し、データに基づいた迅速な意思決定を可能にするこの技術は、あらゆる企業の生産性を向上させ、新たな競争力を生み出すポテンシャルを秘めています。
しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すには、自社の課題に即した戦略的な導入と、現場での活用を定着させる取り組みが欠かせません。もし、AI導入の進め方や具体的な活用方法にお悩みであれば、専門家の知見を活用するのも有効な手段です。AX CAMPでは、貴社の状況に合わせた最適なAI活用プランの策定から、社員のスキルアップ、導入後の定着まで、一気通貫でご支援します。詳しい内容は無料相談にてご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。