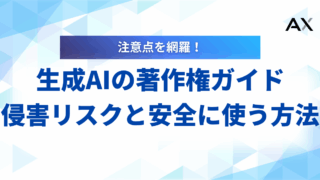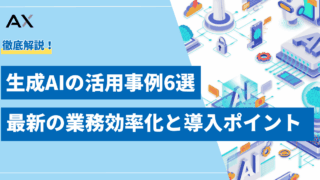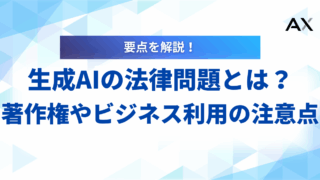「生成AIで作成した画像を、自社のWebサイトや広告で使いたい」
「でも、著作権などの法的なリスクが心配…」
このようにお考えではありませんか?
生成AIによる画像作成は非常に便利ですが、ビジネスで利用する際には、その手軽さの裏に潜むリスクを正しく理解する必要があります。適切なツールを選び、注意点を押さえれば、生成AI画像を安全かつ効果的に商用利用することが可能です。
この記事では、2026年最新の情報に基づき、生成AI画像の商用利用に関する基本から、具体的な活用シーン、法的リスク、そして安全に利用するためのチェックポイントまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、自信を持って生成AI画像をビジネスに活用するための知識が身につきます。
AIのビジネス活用に関して、より実践的な知識や導入支援にご興味のある方は、弊社AX CAMPが提供するサービス資料もぜひご覧ください。貴社の課題解決に繋がるヒントが見つかるかもしれません。
生成AI画像の商用利用とは?基本を解説

結論として、生成AI画像の商用利用は、ツールの利用規約と著作権法を正しく理解し、遵守することで可能になります。ビジネスで活用する前に、まずは基本的な関係性を押さえておくことが重要です。具体的には、「著作権」「商用利用の範囲」「法整備の動向」の3つのポイントを理解する必要があります。
これらの知識が不足したまま利用すると、意図せず他者の権利を侵害し、法的なトラブルに発展するリスクがあります。だからこそ、基本の理解が欠かせません。次のセクションから、各ポイントを詳しく見ていきましょう。
生成AIによる画像と著作権の基本的な関係
AIが自動生成した画像そのものには、原則として著作権が発生しないと解釈されていますが、これはケースバイケースでの判断が必要です。日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、人間の創作的な関与が認められる必要があるためです。(出典:AIと著作権)
例えば、利用者がプロンプト(指示文)に独自の工夫を凝らし、そこに創作性が認められる場合、生成された画像が著作物として保護される可能性も指摘されています。2025年現在の日本の法解釈では、AIが自律的に生成した部分には著作権は発生せず、特定の誰にも帰属しないと考えられています。(出典:AIと著作権に関する考え方について(素案))
ただし、生成された画像が既存の著作物と類似しており、かつ元の著作物を参考にしたという「依拠性」が認められると、著作権侵害が成立する可能性があるため、ビジネス利用では特に注意が必要です。
「商用利用」の定義と具体的な範囲
「商用利用」とは、生成した画像を直接的または間接的に利益を得る目的で使用することを指します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- Webサイトやブログ記事のキービジュアル、挿絵
- SNS投稿、広告バナー、チラシなどのマーケティング素材
- プレゼンテーション資料や企画書の図版
- 商品のパッケージデザインやアパレル製品のプリント
- YouTubeなどの動画コンテンツ内のサムネイルやイラスト
これらの活動はすべて、企業の営利活動の一環と見なされます。そのため、使用する画像生成AIツールの利用規約で「商用利用可」と明記されていることが絶対条件となります。
2025年現在の法整備と業界の動向
生成AIと著作権に関する議論は、技術の進展とともに活発に行われています。文化庁の見解では、AIが学習データを利用する際、著作権法第30条の4に基づき、原則として著作権者の許諾なく利用できると解釈されていますが、これは限定的なケースです。(出典:AIと著作権)
重要なのは、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外となる点です。例えば、違法にアップロードされたコンテンツを学習データとして利用するようなケースは、この例外に該当する可能性があります。2026年時点の法整備は過渡期にあり、学習データの利用には個別の事例判断が必要とされています。
このような状況下で、企業が安全に商用利用するためには、学習データの透明性が高く、著作権侵害のリスクが低いと明言しているサービスを選ぶことが、最も現実的な防衛策と言えるでしょう。
【2026年】商用利用可能なおすすめ画像生成AIツール8選

いざ生成AI画像を商用利用するなら、用途や求める品質、そして何より法的な安全性を基準にツールを選ぶことが成功の鍵です。各ツールには特徴があり、利用規約で定められた商用利用の条件も異なります。ここでは、2026年時点でビジネス利用におすすめの代表的な画像生成AIツールを8つ紹介します。
それぞれのツールの強みと注意点を理解し、自社の目的に最適なものを選びましょう。
1. Adobe Firefly
Adobe Fireflyは、Photoshopなどを提供するAdobe社が開発した画像生成AIです。学習データにAdobe Stockの許諾済みコンテンツや著作権が消滅したパブリックドメインの画像などを使用していると公表しています。
これにより、著作権侵害のリスクが極めて低く、企業が安心して商用利用できる設計となっています。さらに、AdobeはFireflyで生成したコンテンツによって第三者から著作権侵害の申し立てを受けた場合、利用者を法的に保護する「IP補償」を提供しており、ビジネス利用における安全性が非常に高いツールです。Photoshopの「生成塗りつぶし」など、既存のAdobe製品とのシームレスな連携も魅力です。(出典:Adobe Firefly for business)
2. DALL-E 3 (ChatGPT Plus / Copilot Pro)
DALL-E 3は、ChatGPTを開発したOpenAI社による画像生成AIです。ChatGPTの有料プラン(Plus)やMicrosoftのCopilot Proを通じて利用できます。対話形式で直感的に画像を生成・修正できる手軽さが強みです。
OpenAIの利用規約では、ユーザーが生成した画像の所有権はユーザーにあり、商用利用も可能とされています。ただし、生成した画像が第三者の著作権を侵害していないかを確認する責任は利用者にあります。そのため、既存のキャラクターやブランドロゴに酷似した画像が生成されないよう、プロンプトの工夫や生成後のチェックが重要です。(出典:DALL·E API FAQ)
3. Midjourney
Midjourneyは、非常に高品質で芸術性の高い画像を生成できることで定評のあるAIツールです。特に、アートやデザイン、コンセプトアートなどの分野でプロのクリエイターからも高い評価を得ています。
商用利用は有料プランの契約が条件となります。注意点として、年間総収入が100万ドルを超える企業が利用する場合は、より上位の「Pro」プランへの加入が義務付けられています。また、生成した画像が既存の著作物に類似しないように、利用者が注意を払う必要があります。(出典:Midjourney Terms of Service)
4. Stable Diffusion (DreamStudio)
Stable Diffusionは、オープンソースとして公開されている画像生成AIモデルです。ソースコードが公開されているためカスタマイズ性が高く、多くの派生サービスやローカル環境で利用できる点が特徴です。
基本的なモデルは商用利用可能なライセンス(CreativeML Open RAIL-M)で提供されています。しかし、Stable Diffusionの大きな特徴である「追加学習モデル(LoRAなど)」や、参考画像から新たな画像を生成する「img2img」機能を使用する際には注意が必要です。商用利用が許可されていないモデルや、著作権で保護された画像を元に生成した場合、その生成物も商用利用できなくなる可能性があります。(出典:Stable Diffusion Public Release)
5. Canva Magic Media
Canva Magic Mediaは、オンラインデザインツール「Canva」に搭載されている画像生成AI機能です。最大の強みは、Canvaの豊富なデザインテンプレートや編集機能とシームレスに連携できる点です。
生成した画像をそのままプレゼン資料やSNS投稿、広告バナーのデザインに組み込めるため、マーケティング担当者や非デザイナーでも手軽に高品質なクリエイティブを作成できます。基本的に商用利用は許可されていますが、利用前には必ず最新の公式規約を確認することが推奨されます。
6. Shutterstock AI Image Generator
世界最大級のストックフォトサービスであるShutterstockが提供する画像生成AIです。学習データにShutterstockが保有する膨大な量の高品質な画像・イラストを使用しており、生成される画像の品質が安定しています。
生成した画像をダウンロードすると、通常のストックフォトと同様のライセンスが付与され、商用利用が可能です。Adobe Fireflyと同様に、生成した画像に対して知的財産権に関する補償を提供しているため、企業が安心して利用できる選択肢の一つです。(出典:Shutterstock’s AI-generated content is ready and available for license)
7. Leonardo.Ai
Leonardo.Aiは、特にゲームのアセットやコンセプトアートの制作に強みを持つ画像生成AIプラットフォームです。独自の学習モデルや、コミュニティで共有されている多様なカスタムモデルを利用できる点が特徴です。
また、無料プランでも商用利用が可能な点もポイント(無料プランの出力はLeonardoに権利が帰属し、ユーザーは商用利用ライセンスを受ける形/有料プランでは出力の権利がユーザーに帰属)。用途に応じてプランと権利条件を確認しましょう。(出典:Leonardo.Ai)
商用利用の可否や条件は、契約プラン、生成画像の公開・非公開設定、そして使用する学習モデルのライセンスによって細かく異なります。ビジネス利用の際は、必ず最新の利用規約と、利用モデルごとのライセンスを個別に確認することが不可欠です。
8. Getty Images AI Image Generator
Getty Imagesも、Shutterstockと並ぶ大手ストックフォトサービスであり、独自の画像生成AIを提供しています。NVIDIAのPicassoプラットフォーム/Edifyアーキテクチャを用いて構築したGetty独自モデルで、同社のライセンス済み素材を学習しています。
生成された画像には、著作権侵害の心配なく商用利用できるロイヤリティフリーライセンスが付与され、補償が含まれています。コンプライアンスを最優先する大企業にとって、非常に安全性の高い選択肢と言えるでしょう。ツール毎に商用利用の範囲・制約・補償の有無と条件は異なるため、最新の公式規約を必ず確認しましょう。(出典:Getty Images logo)
生成AI画像の主な商用利用の活用シーン
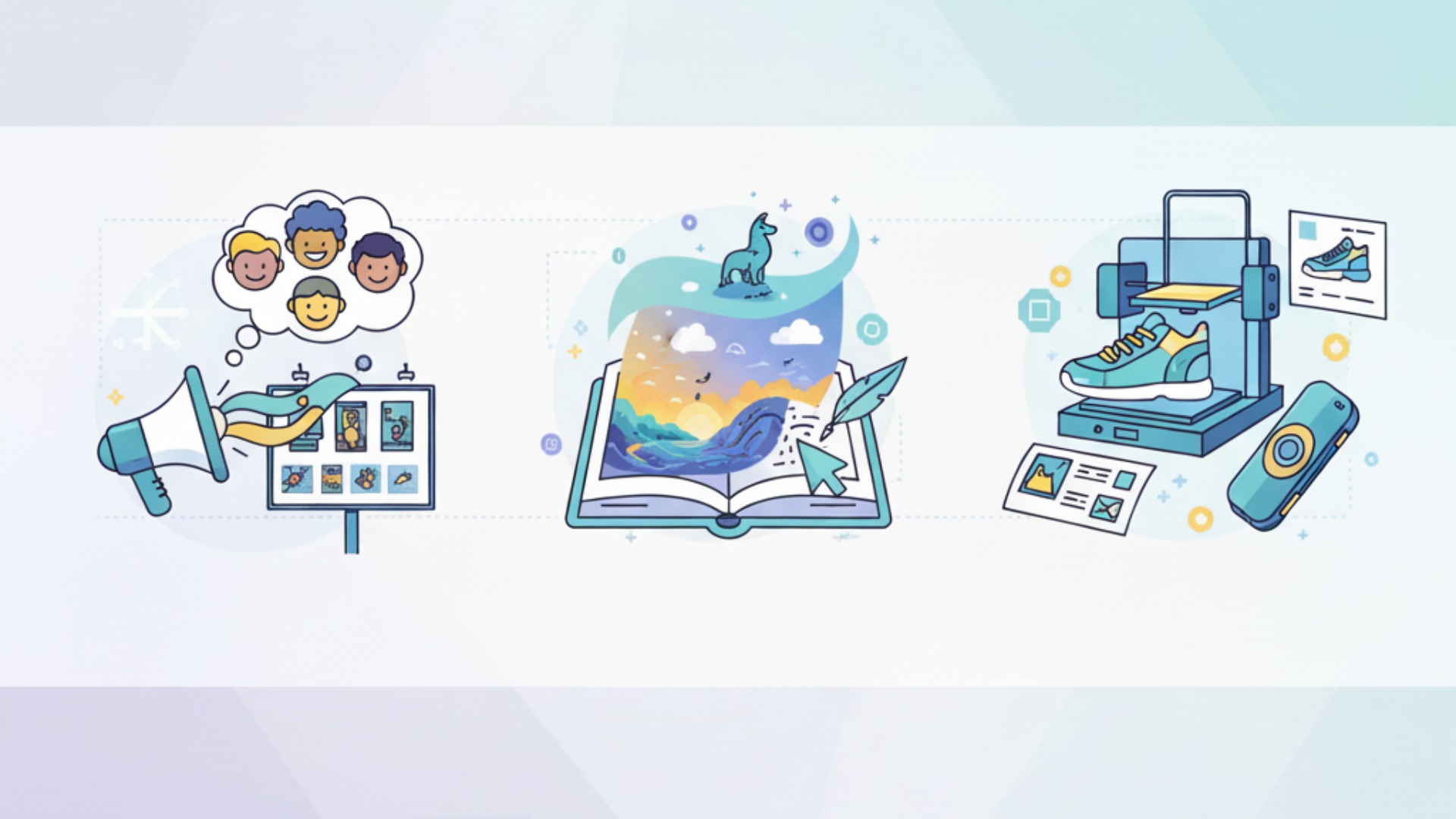
生成AIによる画像作成は、マーケティング、コンテンツ制作、製品デザインなど、ビジネスの様々な場面でコスト削減と時間短縮に大きく貢献します。これまで専門スキルを持つ人材や外注に頼っていた業務を、より迅速かつ低コストで内製化できる可能性を秘めています。
具体的な活用シーンを理解することで、自社のどの業務に適用できるかのヒントが得られるでしょう。実際に、AX CAMPの支援先企業では、AI活用によって大きな成果を上げています。(出典:AI活用事例)
- Webサイト・SNSコンテンツ制作
- 広告・マーケティング素材
- プレゼンテーション資料
- 製品デザインの試作
- ECサイトの商品画像
上記のような場面での活用が考えられます。例えば、ブログ記事の挿絵やSNS投稿用の画像を、外注することなく低コストかつ短時間で作成できます。広告バナーやプレゼンテーション資料に使うイメージ画像を、デザインの専門知識がなくても手軽に用意することも可能です。
Route66様の事例
SNS広告を軸に動画・記事制作を手がける広告代理店のRoute66様は、制作と運用の分業体制で現場が逼迫していました。AX CAMPの導入後、記事原稿の作成を“最大24時間(最短3時間)→AI出力10秒”まで短縮。さらにCanva×AIによるバナー自動生成や通知Botの整備でディレクション工数も圧縮し、ビジュアル制作と確認フローの両面でスループットを向上させました。(出典:AX実績インタビュー「原稿執筆が24時間→10秒に!Route66社が実現したマーケ現場の生成AI内製化」)
C社様の事例
SNSマーケティング事業を手掛けるC社様は、属人化していたSNS運用業務の効率化に課題を抱えていました。AX CAMPの研修を通じてAI自動化システムを内製化した結果、SNS運用にかかる時間を1日平均3時間から1時間へと約66%削減しました。この改善により月間1,000万インプレッションを達成するなど、業務効率と成果の両面で大きな改善を実現しています。(出典:AI活用事例)
エムスタイルジャパン様の事例
美容健康食品の製造販売を行うエムスタイルジャパン様では、コールセンターの履歴確認や広告レポート作成といった手作業に多くの時間を費やしていました。AX CAMPで業務自動化スキルを習得し、コールセンターの確認業務(月16時間)をほぼゼロにするなど、全社で月100時間以上の業務削減に成功しています。(出典:月100時間以上の“ムダ業務”をカット!エムスタイルジャパン社が築いた「AIは当たり前文化」の軌跡)
生成AI画像の商用利用で注意すべき3つの法的リスク

生成AI画像の商用利用は非常に便利ですが、その裏には法的なリスクが潜んでいます。特に注意すべきは「著作権」「商標権」「肖像権・パブリシティ権」の3つの権利侵害リスクです。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じなければ、思わぬ法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。
安全に活用するためには、それぞれの権利がどのようなものか、そしてどのような場合に侵害となる可能性があるのかを正確に把握しておくことが不可欠です。
学習データに起因する著作権侵害リスク
日本では、AIの「学習(情報解析)」は原則として著作権者の許可は不要です(著作権法30条の4)。ただし、生成された画像(出力)が、既存の著作物と似ていて、それに基づくと判断される場合は、著作権侵害と評価される可能性があります。つまり、学習そのものではなく出力の使い方に注意が必要です。公式の考え方は文化庁が公表しているため利用時は確認しておきましょう。(出典:AIと著作権)
利用者が元の著作物の存在を知らなかったとしても、生成された画像と元の著作物との間に「類似性」と「依拠性(元にして作られたこと)」が認められれば、著作権侵害と判断される可能性があります。このリスクを避けるためには、Adobe Fireflyのように、学習データの権利処理がクリーンであることを公表しているサービスを選ぶことが最も有効な対策となります。
生成画像が既存の著作物や商標に類似するリスク
生成AIは、特定のキャラクター、企業のロゴ、デザイン性の高い製品など、既存の著作物や登録商標に似た画像を意図せず生成してしまうことがあります。例えば、有名なアニメキャラクターに酷似したイラストを生成し、自社製品の広告に使用した場合、著作権や商標権の侵害を問われる可能性があります。
これを防ぐためには、プロンプトに特定の作品名やブランド名を含めないことはもちろん、生成された画像が既存の権利を侵害していないか、Googleの画像検索などを利用して類似性チェックを行うことが推奨されます。
実在の人物に似た画像の生成による肖像権・パブリシティ権侵害
生成AIで、実在する特定の人物、特に著名人や有名人に酷似した画像を生成し、無断で公開・利用すると、肖像権やパブリシティ権を侵害するリスクがあります。
「肖像権」は、みだりに自らの容姿を撮影・公表されない権利であり、人格権の一部です。一方、「パブリシティ権」は、有名人の氏名や肖像が持つ顧客誘引力(経済的価値)を保護する権利です。AIで生成した画像であっても、特定の人物だと識別できるレベルで酷似しており、本人の許可なく広告などに利用すれば、これらの権利を侵害する可能性が非常に高くなります。
対策として、プロンプトに実在の人物の名前を入力しないことや、生成画像が特定の個人に似ていないかを確認することが不可欠です。さらに、広告や商品説明に用いる場合は、薬機法(医療・健康に関する表示)や景表法(優良誤認表示)、個人情報保護法に抵触する表現がないかも必ず確認しましょう。
安全に商用利用するためのチェックポイント
生成AI画像をビジネスで安全に活用するためには、「ツールの選定」「利用規約の確認」「生成画像のチェック」という一連のプロセスを徹底することが不可欠です。これらのチェックポイントを組織内でルール化し、担当者全員が遵守することで、法的リスクを大幅に低減できます。
以下に挙げる具体的なチェックリストを活用し、自社の運用体制を見直してみましょう。
- 学習データの透明性:ツールの開発元は、学習データの出典や権利処理について明確に公表しているか?(例:Adobe Firefly, Getty Images AI)
- 利用規約の確認:公式サイトの利用規約やライセンス契約で「商用利用(Commercial Use)」が明確に許可されているか?
- 禁止事項の把握:利用規約に記載されている禁止事項(例:ロゴの生成、違法なコンテンツの作成など)を理解しているか?
- 補償プログラムの有無:万が一の権利侵害トラブルの際に、開発元による法的な補償(Indemnification)は提供されているか?(※適用条件を確認)
- プロンプトの適切性:プロンプトに、既存の著作物名、キャラクター名、ブランド名、実在の人物名など、第三者の権利を侵害する可能性のある単語を含めていないか?
- 生成画像の類似性チェック:生成された画像が、既存のキャラクター、ロゴ、アート作品、写真などに酷似していないか?(Google画像検索などで確認)
- 人物画像の確認:生成された人物の画像が、実在の特定の個人(特に著名人)に酷似していないか?
- 社内ガイドラインの整備:AI生成画像の利用に関する社内ルールを定め、関係者全員に周知しているか?
学習データの透明性は重要ですが、実務では出典の公開範囲、権利処理の公表有無、利用規約の商用利用の明記を総合的に評価することが妥当です。これらのポイントを一つずつ確実にクリアしていくことが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
生成AI 画像 商用利用に関するFAQ

ここでは、生成AI画像の商用利用に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。具体的な疑問点を解消し、より安心してAI活用を進めるための参考にしてください。
無料で生成したAI画像を商用利用できますか?
ツールの利用規約によりますが、無料プランでの商用利用には条件が付く場合が多いです。例えば、Leonardo.Aiは商用利用を許可する場合がありますが、生成画像が公開される、プラットフォーム側に利用権が及ぶ等の制約があります。安全に商用利用するためには、規約で明確に許可されており、かつプライバシーなどが保護される有料プランへの加入を強く推奨します。
生成AIで作成した画像の著作権は誰に帰属しますか?
2025年現在の日本の法解釈では、AIが自律的に生成した部分には著作権は発生せず、特定の誰にも帰属しないと考えられています。著作権は、人間の「思想又は感情を創作的に表現した」ものに与えられるためです。(出典:AIと著作権)
ただし、利用者がプロンプトの選定や指示の出し方、生成後の加工・修正などに創作的な工夫を凝らした場合は、その部分に創作性が認められ、著作物として保護される可能性があります。多くのサービス規約では、生成された画像の権利は利用者に譲渡されると記載されていますが、これはあくまでサービス提供者と利用者間の契約であり、第三者の著作権を侵害していないことを保証するものではない点に注意が必要です。
Adobe Fireflyで生成した画像は安全に商用利用できますか?
はい、Adobe Fireflyは現時点で最も安全に商用利用できる画像生成AIの一つと言えます。その理由は、学習データにAdobe Stockなど権利的にクリーンな画像のみを使用しているため、著作権侵害のリスクが極めて低いからです。
さらに、Adobeは企業向けプランなどを対象に「IP補償」という制度を設けており、Fireflyで生成したコンテンツが原因で第三者から権利侵害を主張された場合、法的な問題解決を支援してくれます。(出典:Adobe Firefly for business) この手厚い保護体制により、特にコンプライアンスを重視する企業にとって、安心して利用できる選択肢となっています。
画像生成AIのビジネス活用ならAX CAMPにご相談ください

生成AI画像の商用利用には、ツールの選定からリスク管理、そして効果的な活用法まで、専門的な知識が求められます。「どのツールが自社に最適かわからない」「法務リスクを考えると、導入に踏み切れない」「具体的にどう業務に活かせば成果が出るのか知りたい」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
このようなビジネス課題の解決をサポートするのが、当社が提供する実践型AI研修「AX CAMP」です。AX CAMPでは、ツールの基本的な使い方だけでなく、ビジネスの現場で成果を出すためのAI活用ノウハウを体系的に学ぶことができます。特に、本記事で解説したような著作権などの法的リスクを回避し、安全にAIを活用するためのリテラシー教育に力を入れています。
各企業の課題に合わせたカリキュラム設計が強みであり、SNS運用を効率化したい、マーケティングコンテンツの制作コストを削減したい、といった具体的なニーズに応えることが可能です。実際に、AX CAMPを受講されたWISDOM合同会社様は、AI導入により採用担当者2名分の業務を代替する成果を上げています。このように、劇的な成果を上げている事例が多数ございます。
専門家の伴走支援を受けながら、自社に最適なAI活用の仕組みを構築しませんか。まずは無料のオンライン相談会で、貴社の課題やAI導入に関するお悩みをお聞かせください。事実に基づいた情報提供と、貴社に合った研修プランをご提案します。
まとめ:生成AI 画像の商用利用を正しく理解しビジネスを加速
本記事では、2026年最新の情報に基づき、生成AI画像の商用利用について、基本知識から具体的なツール、法的リスクと対策までを解説しました。
重要なポイントを以下にまとめます。
- 商用利用の可否はツールの利用規約次第:必ず公式サイトで「商用利用可」であることを確認する。
- 安全性を最優先するなら学習データが重要:Adobe Fireflyなど、権利的にクリーンなデータで学習したツールの利用が推奨される。
- 3つの法的リスクに注意:著作権、商標権、肖像権・パブリシティ権の侵害リスクを常に意識する。
- 利用前のチェックを習慣化:プロンプトの内容や生成された画像の類似性チェックを徹底し、リスクを回避する。
生成AIは、正しく使えばコンテンツ制作のコストと時間を大幅に削減し、ビジネスを加速させる強力な武器となります。しかし、その力を最大限に引き出すには、技術的な側面だけでなく、法務や倫理に関するリテラシーが不可欠です。
「社内にAIを導入したいが、リスク管理や人材育成をどう進めればいいか分からない」という場合は、ぜひ一度、AX CAMPにご相談ください。専門家の知見を活用し、貴社が安全かつ効果的にAIをビジネス活用できるよう、最適な研修プログラムをご提案します。