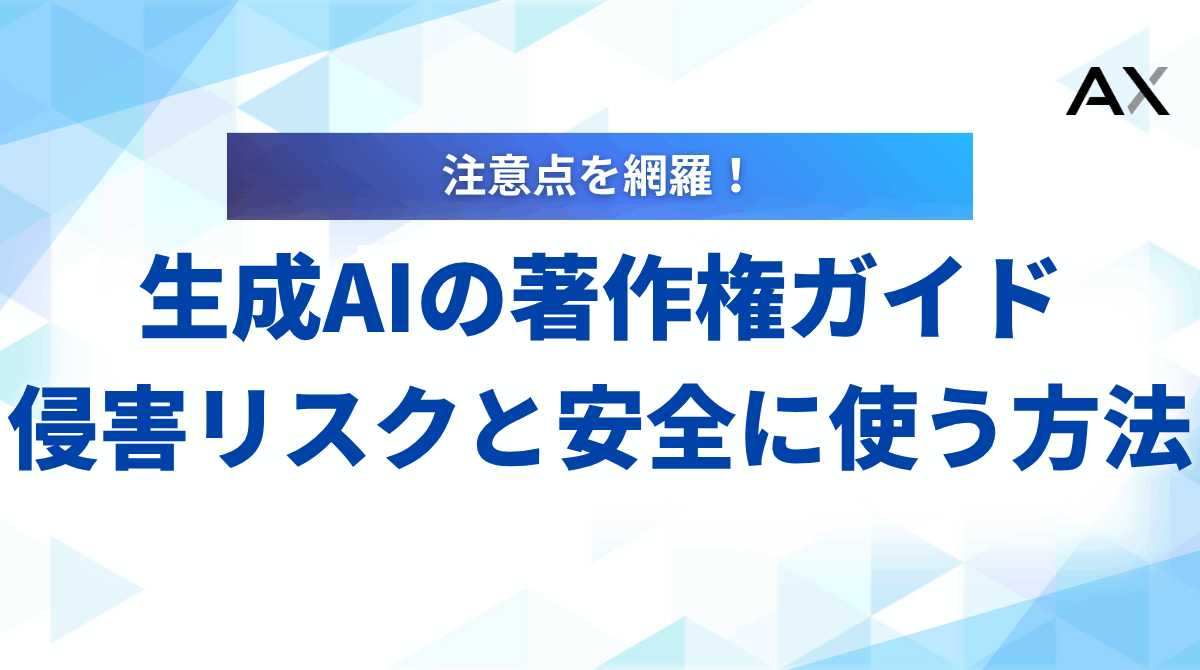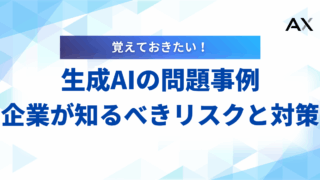「生成AIで作成したコンテンツは、誰かの著作権を侵害していないだろうか」
「ビジネスで安全に使うには、何に気をつければ良いのか」
生成AIの業務活用が広がる一方で、このような著作権に関する不安を抱える企業は少なくありません。万が一、意図せず権利を侵害してしまえば、法的なトラブルに発展するリスクもあります。
しかし、生成AIの著作権に関する法的なポイントと実践的な対策を理解すれば、リスクを管理し、安全にその恩恵を享受することが可能です。著作権の問題は、AIがデータを
「学習する段階」と、コンテンツを「生成・利用する段階」の2つのフェーズで分けて考えることが重要となります。
この記事では、2026年時点の最新の法解釈や文化庁の見解に基づき、生成AIと著作権の基本から、具体的な侵害ケース、ビジネスで安全に利用するための対策までを網羅的に解説します。 読み終える頃には、著作権リスクへの漠然とした不安が解消され、自信を持ってAI活用を推進できるようになるでしょう。
なお、AXCAMPでは、生成AIを使った業務の不安ごとの相談も受け付けています。今後の業務効率化の方向性を検討されてる場合は、下記資料もご参照いただき、AI導入推進にお役立てください。
記事:【AI導入しないことが経営リスクになる時代】先行企業が手にした圧倒的な競争優位とは?
生成AIと著作権の基本関係【2026年時点の法解釈】

生成AIと著作権の関係性を理解する上で最も重要なのが、日本の著作権法です。特に、技術革新に対応するために設けられた「著作権法第30条の4」が中心的な役割を果たします。この条文は、AI開発のような情報解析を目的とする場合、一定の条件下で著作権者の許諾なく著作物を利用できると定めています。(出典:平成30年著作権法改正について | 文化庁)
この法律のポイントは、AIと著作権の問題を「AIがデータを学習する段階」と「AIがコンテンツを生成し、それを利用する段階」という2つの異なるフェーズで捉えている点です。学習段階では技術開発の促進を目的として柔軟な対応が認められる一方、生成・利用段階では従来の著作権法と同様の考え方が適用されます。この区別を理解することが、リスクを正しく判断する第一歩と言えるでしょう。
著作権法第30条の4の概要と目的
著作権法第30条の4は、2018年の法改正で導入された「柔軟な権利制限規定」の一つです。この条文が目指すのは、AI開発やビッグデータ解析といった新しい技術の発展を、著作権法が過度に妨げないようにすることにあります。(出典:平成30年著作権法改正について | 文化庁)
具体的には、著作物に表現された思想や感情を「享受(楽しむこと)」する目的でなければ、必要と認められる限度において、著作権者の許可なく著作物を利用できると定めています。ただし、これには「著作権者の利益を不当に害さないこと」という重要な但し書きがあり、無制限に利用が認められるわけではありません。個別の事情によって適用の可否が判断されるため、但し書きや収集経路、契約上の制約などにも注意が必要です。
文化庁が示す「AIと著作権に関する考え方」の要点
法解釈の具体的な指針として、文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」という資料を公表しています。これは、現行法の下でどのような行為が許容され、どのような行為が著作権侵害のリスクを伴うのかを、具体例を交えて示したものです。(出典:AIと著作権 | 文化庁)
この資料の要点は、前述の通り「学習段階」と「生成・利用段階」を明確に分けてリスクを判断している点です。学習段階では第30条の4に基づき原則として適法としつつも、「著作権者の利益を不当に害する場合」は違法となる可能性を指摘しています。一方で、生成・利用段階では、生成物が既存の著作物と類似しているか(類似性)、そして既存の著作物を基にして作られたか(依拠性)という、従来の著作権侵害の判断基準が適用されることを明確にしました。この考え方は、企業がAI利用のガイドラインを作成する上で、非常に重要な拠り所となります。
AIの「学習段階」における著作権の論点

生成AIが人間のようなコンテンツを生み出すためには、膨大な量のデータを学習する必要があります。この「学習段階」において、インターネット上にある文章、画像、音楽といった著作物を利用することが、著作権法上どのように扱われるのかが重要な論点です。
日本の著作権法では、この学習行為は原則として適法と解釈されやすい状況にあります。これは、AI開発という技術的な目的のための利用であり、個々の著作物を鑑賞する「享受」目的ではないためです。しかし、学習データの取得方法が適法であるかなど、注意すべき点も存在します。
原則として適法な「情報解析」目的の学習
AIによるデータ学習は、著作権法第30条の4で定められた「情報解析」の目的に該当する場合があります。この条文によれば、大量の著作物から言語のパターンや画像の特徴といった情報を抽出し、解析する行為は、著作権者の許諾が不要とされています。(出典:平成30年著作権法改正について | 文化庁)
この規定は、AI開発が非営利目的か営利目的かを問いませんが、利用方法や入手経路、契約条項、データベース権の有無を個別に確認する必要があります。例えば、学習データの入手方法が違法なサイトからのダウンロード(違法アップロードと知りながらのダウンロード)や、利用規約に違反したスクレイピングなどであった場合、著作権法違反とは別の問題が生じる可能性があるため、注意が求められます。
「著作権者の利益を不当に害する場合」の例外
ただし、学習目的の利用が無制限に認められるわけではありません。著作権法第30条の4には但し書きがあり、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、この権利制限規定が適用されないと定められています。(出典:平成30年著作権法改正について | 文化庁)
例えば、本来有料で販売されている学習用データセットを、海賊版サイトなどから不正な手段で入手してAIの学習に利用するようなケースがこれに該当する可能性があります。また、特定の作家の作品ばかりを意図的に大量に学習させ、その作家の作風に酷似したコンテンツを生成する目的で利用する場合なども、著作権者の利益を不当に害すると判断されるリスクが高まります。企業としては、学習データの入手元が適法であることを確認し、特定の権利者に不利益を与えるような学習方法を避ける必要があります。
AIの「生成・利用段階」における著作権の論点
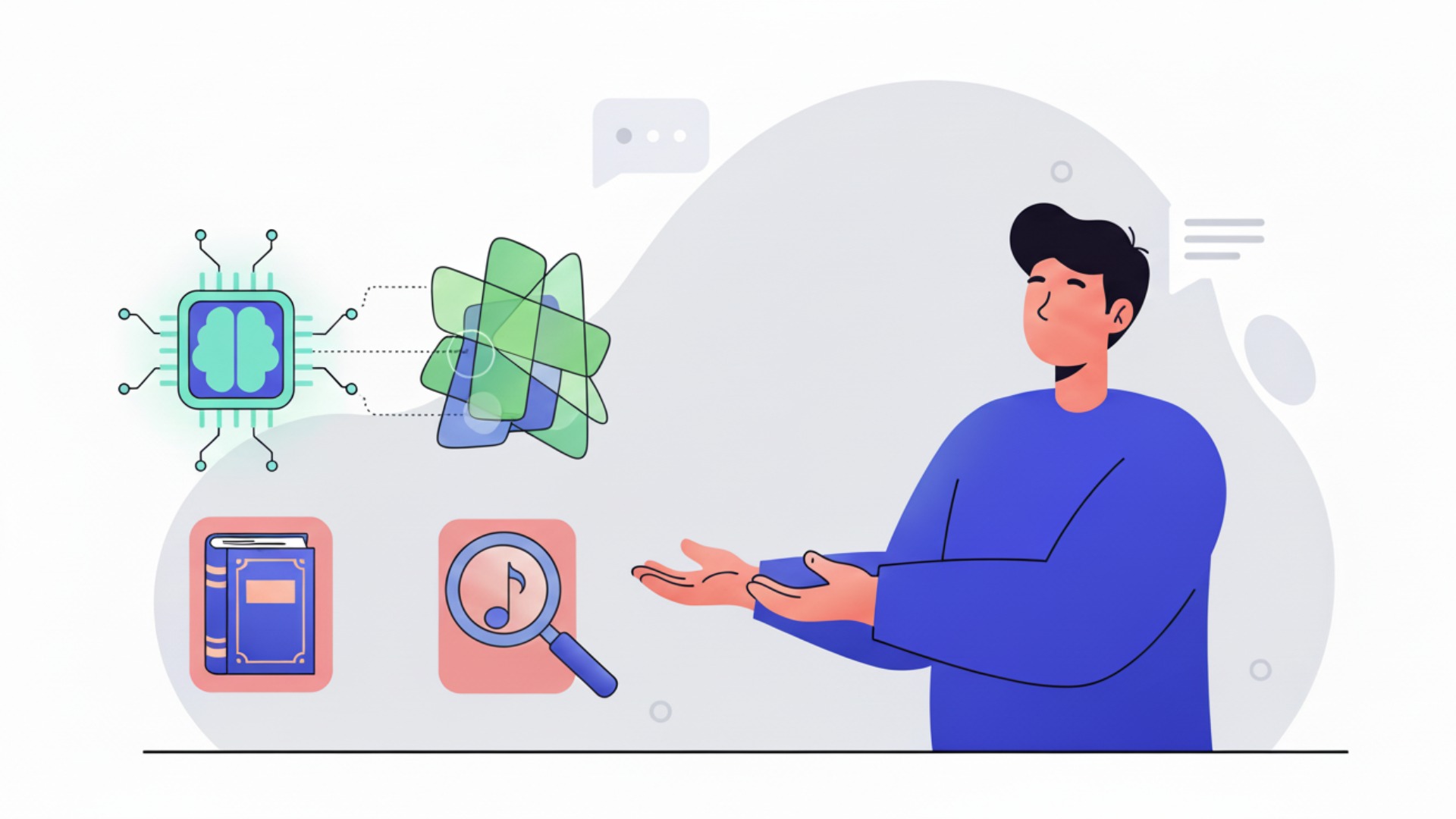
AIの学習段階とは異なり、AIが生成したコンテンツを実際に利用する「生成・利用段階」では、全く異なる著作権の考え方が適用されます。この段階で最も注意すべきは、生成物が既存の著作物と似ていないかという点です。
たとえAIが自動で生成したものであっても、結果的に誰かの著作物と酷似していれば、著作権侵害と判断される可能性があります。特に、生成物を商用利用する場合は、類似性の調査を必須プロセスとして組み込むなど、より慎重な確認が求められます。
生成物が既存の著作物と類似した場合のリスク
AIが生成したイラスト、文章、音楽などが、既存の著作物と表現上の本質的な特徴において共通している場合、「類似性」があると判断されます。さらに、その生成過程でAIが元の著作物を学習しており、それに基づいて生成したと認められる場合は「依拠性」があるとされます。この「類似性」と「依拠性」の両方が認められると、著作権侵害が成立します。
日本ではまだ判例の蓄積が限定的で、実務上はケースバイケースの判断となることが多いのが現状です。そのため、文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方」や、後述する海外の訴訟動向などを参考に、自社のリスクを判断していく必要があります。(出典:AIと著作権 | 文化庁)
生成物の商用利用における注意点
生成物をビジネスで利用する場合、著作権侵害のリスクはさらに高まります。個人的な利用(私的利用)の範囲であれば問題とならないケースでも、商用利用となると権利者の許諾が必要になるのが原則です。
企業がAI生成物を広告、商品デザイン、ウェブコンテンツなどに利用する際は、事前に類似する既存の著作物がないかを確認するプロセスが不可欠です。特に画像の場合は、画像検索ツールなどを用いてチェックすることが有効な対策となります。また、利用するAIサービスの規約で、生成物の商用利用が許可されているかを確認することも必ず確認しましょう。
生成AIによる著作権侵害と判断されるケースとは?

生成AIの利用が著作権侵害にあたるかどうかは、最終的に「依拠性」と「類似性」という2つの要件を満たすかによって判断されます。この2つの要件は、AIが関与しない従来の著作権侵害の判断基準と同じです。AIだから特別扱いされるわけではない、という点を理解することが重要です。
つまり、AIが生成したコンテンツが、たまたま既存の作品と似てしまっただけでは、直ちに著作権侵害とはなりません。元の作品の存在を知った上で、それに基づいて創作されたという関係性が認められて初めて、侵害の問題が生じるのです。
侵害の要件①:依拠性(既存の著作物をもとにしたか)
「依拠性」とは、既存の著作物を参考に、あるいはその知識に基づいて創作したことを意味します。生成AIの文脈では、AIが学習データとして特定の著作物を読み込み、その情報が生成プロセスに影響を与えた場合に依拠性が認められる可能性があります。
例えば、特定のイラストレーターの作品名をプロンプトに含めて画像を生成し、その結果、そのイラストレーターの作品に酷似したものが出来上がった場合、依拠性が認められやすくなります。ユーザーが既存の著作物の存在を知らなかったとしても、AIがそれを学習していれば、依拠性があると判断される可能性があるため注意が必要です。
侵害の要件②:類似性(表現上の本質的な特徴が共通しているか)
「類似性」とは、2つの作品を比べた際に、表現上の本質的な特徴が共通していることを指します。単にアイデアやコンセプト、作風が似ているだけでは類似性があるとは言えず、著作権侵害にはなりません。あくまで、具体的な表現が似ているかどうかが問われます。
例えば、「夕日を背景にした猫のイラスト」というアイデア自体は誰でも自由に利用できます。しかし、特定のイラスト作品における猫のポーズ、表情、背景の構図、色彩といった具体的な表現が酷似している場合、類似性が認められ、著作権侵害となる可能性が高まります。
AI生成物は「著作物」として認められるのか?
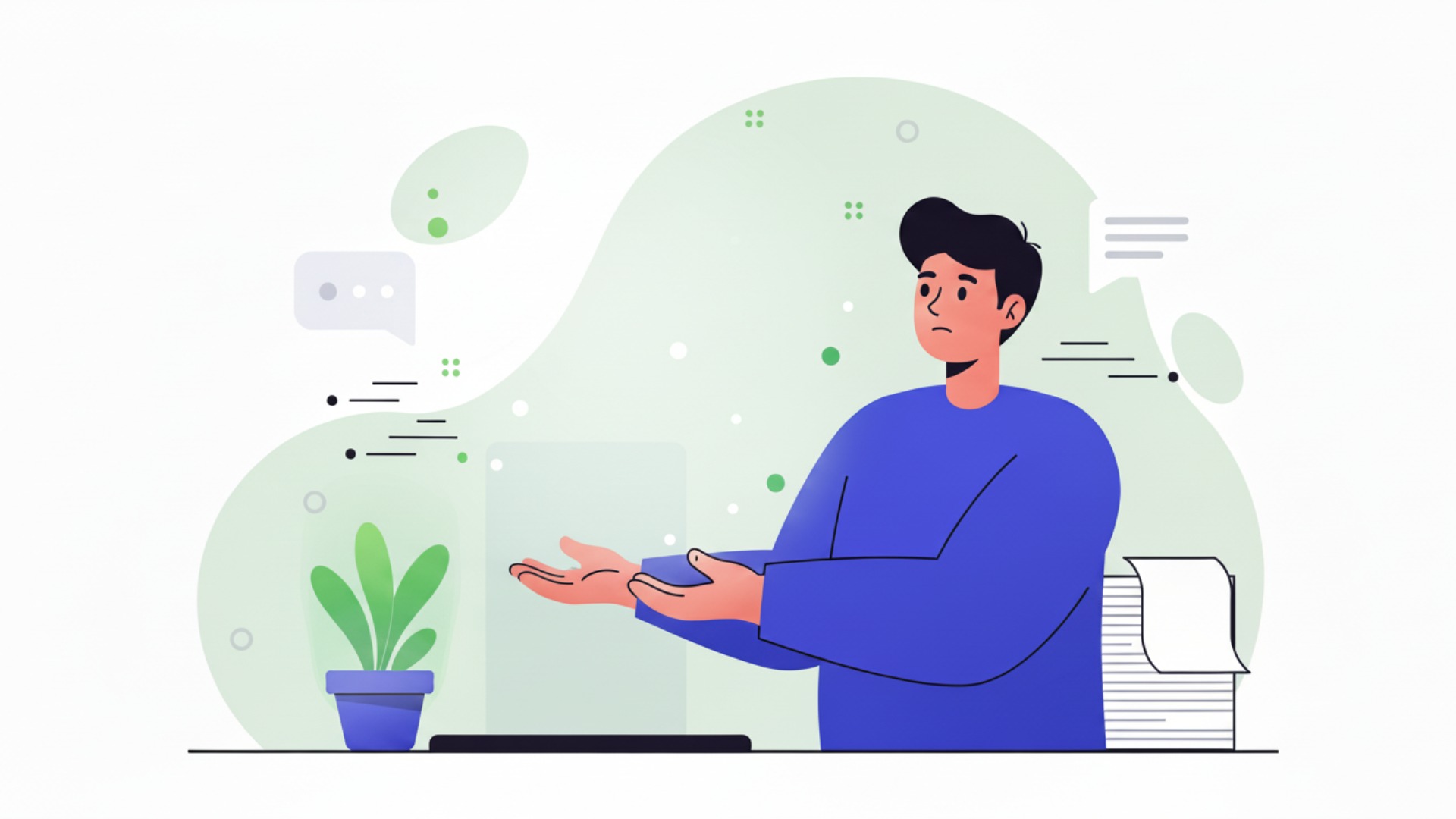
生成AIによって作られたコンテンツが、それ自体「著作物」として著作権法で保護されるのか、という点も重要な論点です。結論から言うと、AIが自動的に生成しただけのものは、原則として著作物とは認められません。著作権が発生するためには、そこに関与した「人間」の創作的な貢献が必要不可欠です。
この判断基準を理解することは、自社でAIを用いて作成したコンテンツの権利を守る上で、また、他者のAI生成物を利用する際にも重要となります。
人間の「創作的寄与」の有無が判断基準
AI生成物が著作物と認められるかどうかは、その生成過程における人間の「創作的寄与」があったかどうかで決まります。創作的寄与とは、単なる作業や簡単な指示を超えて、人間の思想や感情が創作的に表現されるための具体的な貢献を指します。
例えば、AIに対して「猫の絵を描いて」と簡単な指示を与えただけで生成された画像は、人間の創作的寄与が認められにくく、著作物とは言えません。一方で、プロンプトを何度も試行錯誤して調整したり、AIが生成した複数の案から最適なものを選択・結合したり、生成後に画像編集ソフトで大幅な加筆修正を加えたりした場合は、一連の行為全体として創作的寄与が認められ、その結果物が著作物となる可能性があります。
プロンプト(指示文)の著作物性について
AIに与える指示文である「プロンプト」自体が、著作物として保護される可能性もあります。そのためには、プロンプトが単なる単語の羅列や短い指示ではなく、それ自体に創作的な表現が含まれている必要があります。
例えば、詩や短編小説のように、表現に工夫が凝らされた長文のプロンプトであれば、プロンプト自体が言語の著作物として認められる余地があります。しかし、一般的なプロンプトの多くは、AIへの指示という機能的な側面が強く、創作的な表現とは言えないため、著作物として保護されるのは限定的なケースと考えられます。
【国内外】生成AIの著作権に関する主要な事案

生成AIの著作権をめぐる議論は、法廷での争いに発展するケースも増えています。これらの事案は、今後の法解釈や企業の取るべき対策に大きな影響を与えるため、動向を注視することが重要です。特に、学習データの利用方法や生成物の類似性が大きな争点となっています。
ここでは、世界的に注目を集めている主要な訴訟事例をいくつか紹介します。
ニューヨーク・タイムズ vs OpenAI & Microsoft
米大手新聞社ニューヨーク・タイムズが、自社の記事が許諾なくChatGPTの学習に利用され、著作権を侵害されたとして、開発元のOpenAIとパートナーのMicrosoftを提訴した事例です。報道機関がAI開発企業を大規模に訴えた初のケースとして注目されており、AIの学習データ利用の公正性(フェアユース)が最大の争点となっています。(出典:米 NYタイムズ “記事を無断でAIの学習に利用” OpenAIなど提訴 | NHK)
ゲッティイメージズ vs Stability AI
世界最大級のストックフォトサービスであるゲッティイメージズが、画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元Stability AIを提訴した事例です。ゲッティイメージズが権利を持つ1,200万点以上の画像が、許可なく学習データとして利用されたと主張しています。生成された画像にゲッティイメージズの透かし(ウォーターマーク)が残っていたことも問題視されており、学習データの無断利用が直接的な被害につながることを示す象徴的な事案です。(出典:画像AI「Stable Diffusion」開発元、Getty Imagesに提訴される – PC Watch)
アーティストによる集団訴訟
米国では、複数のアーティストが、MidjourneyやStable Diffusionなどの画像生成AIが自分たちの作品を無断で学習し、作風を模倣した画像を生成しているとして、開発企業を相手に集団訴訟を起こしています。この訴訟は、個々の作品の類似性だけでなく、アーティストの「スタイル(作風)」の模倣が法的にどう扱われるかという、新たな論点を含んでいます。
ビジネスで生成AIを安全に利用するための実践的対策

生成AIをめぐる著作権リスクは複雑ですが、企業が適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に低減させることが可能です。重要なのは、法的な知識を持つことと、それを社内の運用ルールに落とし込むことです。「規約の確認」「生成物のチェック」「社内ガイドラインの策定」の3つが、安全なAI活用のための柱となります。
これらの対策を徹底することで、法的トラブルを回避し、安心して生成AIがもたらす生産性向上のメリットを享受できます。
利用する生成AIサービスの利用規約を必ず確認する
最も基本的かつ重要な対策は、利用する生成AIサービスの利用規約を熟読し、遵守することです。規約には、生成物の著作権が誰に帰属するのか、商用利用は許可されているのか、学習データにインプットした情報がどのように扱われるのか、といった重要事項が記載されています。
サービスによっては、生成物の商用利用を禁止していたり、特定の条件下でのみ許可していたりする場合があります。また、入力した機密情報がAIの再学習に使われないようにする設定(オプトアウト)の有無も必ず確認すべき項目です。規約を軽視すると、意図せず契約違反や情報漏洩につながる恐れがあります。
生成物と既存作品の類似性をチェックする
特に画像やデザイン、音楽などを生成AIで作成し、商用利用する場合には、既存の作品と類似していないかを確認するプロセスを業務に組み込むことが不可欠です。前述の通り、AIが生成したものであっても、既存の著作物との間に「類似性」と「依拠性」が認められれば著作権侵害となります。
具体的なチェック方法としては、Googleなどの画像検索機能を使って類似の画像がないかを確認したり、業界専門のデータベースで既存のデザインを調査したりする方法があります。この一手間を惜しまないことが、将来の紛争リスクを回避するために極めて重要です。
社内での生成AI利用ガイドラインを策定する
従業員が個々の判断で無秩序に生成AIを利用すると、著作権侵害や情報漏洩のリスク管理が困難になります。そこで、全社共通の生成AI利用ガイドラインを策定し、従業員に周知徹底することが求められます。
ガイドラインに盛り込むべき項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 利用を許可するAIツールとその範囲
- 機密情報や個人情報の入力禁止
- 著作権を侵害するようなプロンプト(例:「〇〇(作家名)風に」)の禁止
- 生成物を商用利用する際のチェック体制と承認プロセス
- 問題が発生した際の報告ルート
このようなルールを明確に定めることで、組織全体でリスクを統制し、安全なAI活用文化を醸成することができます。
主要な生成AIサービスの利用規約と著作権ポリシー

生成AIサービスを選ぶ際には、機能や料金だけでなく、その利用規約や著作権ポリシーを比較検討することが非常に重要です。サービスによって、生成したコンテンツの権利の扱いが大きく異なるため、自社の利用目的に合ったサービスを選ぶ必要があります。特に「生成物の著作権の帰属」と「商用利用の可否」は必ず確認すべきポイントです。
以下に、主要な生成AIサービスの著作権に関するポリシーをまとめました。ただし、規約は頻繁に更新されるため、利用前には必ず公式サイトで最新の規約(2025年9月時点)を確認してください。
| サービス名 | 開発元 | 生成物の著作権 | 商用利用 | 学習データへの利用 |
|---|---|---|---|---|
| GPTシリーズなど | OpenAI | ユーザーに帰属 | 可(規約遵守が条件) | アカウント種別や設定に依存(オプトアウト可能) |
| Geminiなど | ユーザーに帰属(Googleは所有権を主張しない) | 可(規約で明確に禁止されていない) | オプトアウト可能 | |
| Claudeシリーズなど | Anthropic | ユーザーに帰属 | 可 | 商用アカウントはデフォルトで利用しない。消費者向けはユーザーが選択可能 |
| Midjourney | Midjourney | 有料プランユーザーに帰属(詳細は要規約確認) | 有料プランで可 | 利用規約に基づく |
| Canva AI | Canva | ユーザーに帰属 | 可(Canvaの利用規約の範囲内) | サービス改善のために利用 |
今後の法改正の動向と将来の展望

生成AIと著作権に関する法制度は、まだ発展途上にあります。技術の急速な進化に法整備が追いついていないのが現状であり、今後、国内外で新たなルール作りが進んでいくことは確実です。企業は、法改正の動向を継続的にウォッチし、社内ガイドラインを柔軟に見直していく姿勢が求められます。
日本では、文化庁の審議会で引き続き議論が重ねられており、将来的には著作権法そのものが改正される可能性もあります。また、海外の動向、特にEUの「AI法」や米国の判例の積み重ねは、日本の法制度にも大きな影響を与えると考えられます。例えば、学習データに関する透明性の確保や、AI生成物であることを明示する義務などが、国際的な標準となる可能性も視野に入れておくべきでしょう。
このような変化の激しい時代においては、最新の情報を常に収集し、法務部門と事業部門が連携してリスクに対応できる体制を構築しておくことが、企業の持続的な成長にとって不可欠です。
生成AIの著作権リスクを正しく学びたいならAX CAMP

生成AIの著作権リスクは複雑で、法改正の動向も常に変化しています。こうした専門的な知識を独学でキャッチアップし、自社の状況に合わせた最適なガイドラインを策定するのは容易ではありません。安全かつ効果的にAI活用を進めるためには、専門家の知見を取り入れ、体系的に学ぶことが最も確実な近道です。
私たちAX CAMPが提供する法人向けAI研修では、技術的なスキル習得だけでなく、ビジネス活用に不可欠な著作権などの法務・倫理リスクについても、最新の動向を踏まえた実践的なカリキュラムを提供しています。経験豊富な専門家が、貴社の事業内容や課題に合わせて、明日から使えるAI活用術と、安心して導入するためのリスク管理体制の構築をサポートします。
「自社の場合、どのような点に注意すれば良いのか」「従業員のリテラシーをどう向上させれば良いのか」といった具体的なお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な研修プランをご提案します。
まとめ:生成AIの著作権を理解し、創造的な活用を目指そう
本記事では、生成AIと著作権に関する2026年時点での最新情報と、企業が取るべき実践的な対策について解説しました。改めて、重要なポイントを以下にまとめます。
- 学習と利用のフェーズ分離:AIによる著作物の扱いは「学習段階」と「生成・利用段階」で異なり、学習は一定の条件下で適法、利用は従来の著作権法が適用されます。
- 侵害の2要件:生成物が著作権侵害となるかは、既存の著作物との「依拠性」と「類似性」の両方を満たすかで判断されます。
- 人間の創作的寄与が鍵:AI生成物が著作物として保護されるかは、プロンプトの工夫や生成後の編集といった人間の「創作的寄与」の有無で決まります。
- 企業の3つの防衛策:安全な活用のためには、「利用規約の確認」「類似性チェック」「社内ガイドライン策定」が不可欠です。
生成AIは、正しく理解し活用すれば、ビジネスに革命的な変化をもたらす強力なツールです。著作権リスクを過度に恐れて活用をためらうのではなく、本記事で紹介したような知識を身につけ、適切なリスク管理を行うことで、その恩恵を最大限に引き出すことができます。
AX CAMPでは、こうした著作権リスクへの対応も含め、AIを安全に活用し、具体的な業務成果に繋げるための実践的な法人研修を提供しています。専門家の支援を受けながら、AI導入の第一歩を確実に踏み出したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。